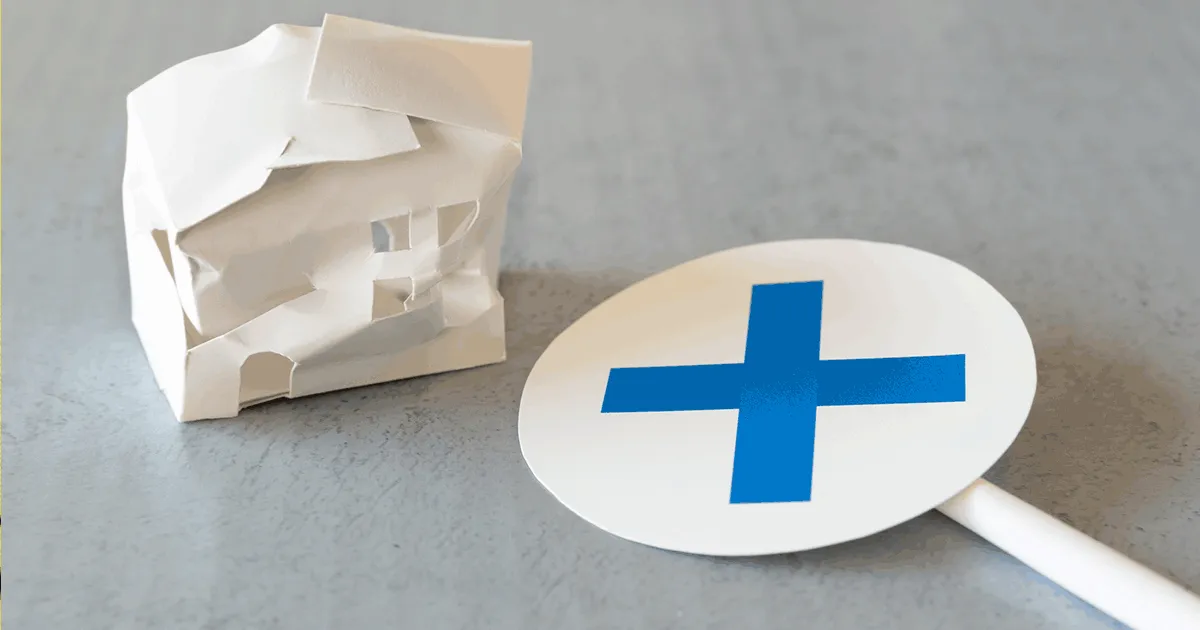はじめに
近年、全国的に空き家の増加が深刻な社会課題となっています。特に都市近郊では、空き家が犯罪の温床となるケースもあり、所有者には早急な対応が求められています。
本記事では、空き家を放置することで生じる7つのリスクを解説し、併せて空き家の活用や処分方法についても紹介します。空き家を所有しており、将来的な管理に不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。
不動産相続の全体像については、こちらの総合記事もあわせてご覧ください。
第1章 空き家を放置する7つのリスク
1-1 建物が傷んでしまう
空き家を長期間放置すると、室内の換気がされず湿気がたまりやすくなります。特に木造住宅では、木材の腐食やカビの発生が進み、建物全体の劣化スピードが加速します。また、雨漏りや外壁のひび割れといった損傷にも気づかないまま放置されるため、補修が難しくなることもあります。
加えて、害虫や小動物の住処になりやすく、衛生面の問題も発生します。こうした要因により、建物の資産価値は大きく低下することになります。
1-2 建物の倒壊リスクが発生する
老朽化が進んだ空き家は、台風や地震などの自然災害に耐えられず、倒壊する危険性があります。特に屋根や外壁が崩れ落ちると、隣家や通行人への被害につながる可能性も否めません。
このような事故が発生した場合、所有者には民法上の損害賠償責任が生じる可能性があり、数百万円から数千万円の請求につながるケースもあります。
1-3 近隣からのクレームや訴訟リスクがある
空き家の見た目の悪化や害虫の発生、不審者の侵入などにより、周囲の住民に迷惑をかける事態が生じやすくなります。これにより、クレームや苦情が相次ぎ、自治体や警察への相談に発展するケースもあります。
問題を放置し続けると、訴訟や損害賠償請求につながる恐れもあり、金銭的負担や精神的ストレスを抱えることになります。
1-4 空き家が犯罪に使われる恐れがある
空き家は人目が少なく、犯罪者にとって都合の良い場所になりがちです。実際に、不法投棄、放火、薬物の密売や保管場所などに悪用される事例が報告されています。
一度犯罪が起きると周辺住民の不安が高まり、地域全体の治安が悪化します。
なお、通常の火災保険は、空き家が対象にならないものが多いため、現在の火災保険の契約内容を確認しておくようにしましょう。
1-5 行政から指導が入る恐れがある
空き家の管理が行き届いていない場合、自治体から指導や勧告を受けることがあります。特に、倒壊や衛生リスクがあると判断されると、「特定空家等」に指定され、修繕・解体の命令が下される場合もあります。
命令に従わない場合、行政代執行により強制的に解体され、費用は所有者負担となるため注意が必要です。
また、「特定空家等」に指定されると、それまで適用されていた固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が大幅に増加する恐れがあります。これは所有者にとって経済的な負担の増加につながります。
1-6 固定資産税や管理コストがかかり続ける
空き家を所有している限り、誰も住んでいなくても固定資産税や都市計画税が課税され続けます。さらに、雑草の除去や建物の清掃、破損箇所の補修といった維持管理コストも無視できません。
こうした費用は積み重なると大きな負担となり、将来的に空き家の処分を一層困難にする可能性があります。
1-7 固定資産税が6倍になる恐れがある
管理が不十分な空き家は、「特定空家等」や「管理不全空家等」に指定されることがあり、これにより住宅用地の特例が解除されると、固定資産税の課税額が最大6倍に跳ね上がることがあります。
特に2023年12月の法改正により、これまで軽減措置の対象だった空き家にも厳しい税制が適用されるようになり、放置による経済的リスクはより深刻になっています。
第2章 使用予定のない空き家を活用・処分する方法
2-1 他人に貸し出す
空き家を賃貸物件として貸し出すことで、家賃収入が得られるうえ、建物の劣化も抑えることができます。住人がいれば通気や清掃も行われ、管理状態が保たれやすくなります。
ただし、貸し出すにはリフォームが必要な場合が多く、初期費用として150〜500万円程度がかかることがあります。補助金を用意している自治体もあるため、活用を検討してみましょう。
2-2 空き家を解体し更地にして貸し出す
空き家を解体して更地にすることで、駐車場や資材置き場として活用できます。老朽化が著しい建物を維持するよりも、管理や安全面での負担が軽くなるメリットがあります。
解体費用は30坪で90〜240万円程度が相場とされており、自治体によっては補助制度もあります。注意点として、更地にすると固定資産税の軽減が受けられなくなるため、収支計画は慎重に行いましょう。
2-3 空き家を売却する
空き家の売却は、手間とコストから解放される手段として有効です。不動産会社を通じての仲介売却や、買取業者による即時売却など複数の選択肢があります。
相続物件の場合は、売却の前提として相続登記が必要です。また、売却時には仲介手数料や譲渡所得税、登記費用などの費用が発生します。
なお、相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用される可能性があります。制度の適用条件や手続きについては、あらかじめ専門家に相談して確認しておくと安心です。
2-4 空き家を解体して売却する
建物が古く利用価値がない場合には、解体してから売却することで土地の価値を引き出せる場合があります。ただし、解体後に「再建築不可」の土地であることが判明するリスクには注意が必要です。
再建築不可とは、建築基準法の接道義務を満たさない土地で、新築が許可されない状態を指します。このような土地は買い手が限定されるため、売却価格が下がる可能性があります。
2-5 相続放棄する
空き家を含む相続財産を放棄することで、管理責任や固定資産税から解放されます。相続放棄は、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
ただし、空き家だけでなく、すべての相続財産を放棄することになるため、他に有益な資産がある場合は慎重に判断することが求められます。
2023年4月に施行された民法の改正により、相続放棄をした後の管理責任についての取り扱いが明確になりました。放棄した相続人が空き家を実際に占有していなければ、原則として管理義務は生じません。
なお、相続人全員が放棄を選択した場合、その空き家は「所有者不明土地」として扱われることになり、最終的に国へ引き渡される可能性があります。この手続きを進めるには相続財産管理人の選任が必要で、相応の費用と時間を要する点に注意が必要です。
2-6 寄付・贈与する
空き家を地域のNPO法人や福祉団体、あるいは親族に寄付・贈与することで、管理の負担から解放されます。ただし、受け取り側の同意と意思確認が必要です。
贈与税が発生する可能性もあるため、事前に税理士や専門家への相談が望まれます。また、贈与契約書や所有権移転登記などの法的手続きも忘れずに行いましょう。
2-7 空き家を解体し相続土地国庫帰属制度を利用する
この制度では、相続または遺贈で取得した土地を国に引き渡すことができます。ただし、建物のない更地であることが条件となるため、空き家は解体が前提です。
法務局への申請には、審査手数料や10年分の管理費相当額の負担金が必要です。また、担保権が設定されている土地や、土壌汚染がある土地については申請が却下されます。
申請が承認されれば、国に所有権が移り、管理責任が解消されます。
第3章 【注意】空き家の活用・処分をする際には相続登記を済ませる必要がある
空き家の売却や賃貸、寄付などの手続きを行う際には、前提として「相続登記」が完了していることが重要です。
3-1 相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から、相続による不動産取得に関して「相続登記の義務化」が施行されました。これにより、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行うことが法律で義務付けられています。
正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また、相続登記が未了の状態では、不動産を売却したり、活用・処分したりといった各種手続きが進められないことがあります。早急な手続きが不可欠です。
3-2 相続登記に必要な書類と手続き
相続登記を行うには、以下のような書類が一般的に必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(または遺言書など)
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書
これらの書類をそろえて、管轄の法務局に登記申請を行います。手続きはご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識が求められるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
3-3 登記の有無で生じる差とは?
相続登記を済ませていない場合、不動産を売却しようとしても「まずは相続登記をしてください」と不動産会社に断られてしまいます。また、複数人での共有名義になっているケースでは、相続人どうしの話し合いが必要となるため、時間がかかることもあります。
加えて、相続登記を怠ることで、将来的にトラブルの原因になることもあります。例えば、次世代の相続時にさらに相続人が増えて関係が複雑化し、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。
まとめ
空き家を放置することは、建物の老朽化や倒壊リスク、近隣住民とのトラブル、さらには犯罪への悪用といった、さまざまな深刻な問題を引き起こす可能性があります。放置が続けば、行政からの指導や勧告、固定資産税の増額といった経済的負担も加わり、状況はさらに悪化していきます。
一方で、空き家は適切に活用または処分することで、資産としての価値を回復させることが可能です。賃貸や売却、解体、更地利用、寄付・贈与、相続放棄や国への帰属制度など、選択肢は多岐にわたります。ご自身やご家族の状況に合わせて最適な方法を選び、早めに対応を検討することが重要です。
また、2024年4月からは相続登記が義務化されており、未登記のままでは売却や処分が進められないばかりか、法的な責任やペナルティの対象となる可能性もあります。空き家に関する手続きを円滑に進めるためにも、まずは相続登記の完了を目指しましょう。
「住まいの賢者」では、司法書士や税理士と連携し、相続登記・遺産分割協議書作成・売却手続き・税務申告などを一括でサポートしております。
まずは無料相談にて、お悩みや現状をお気軽にご相談ください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。