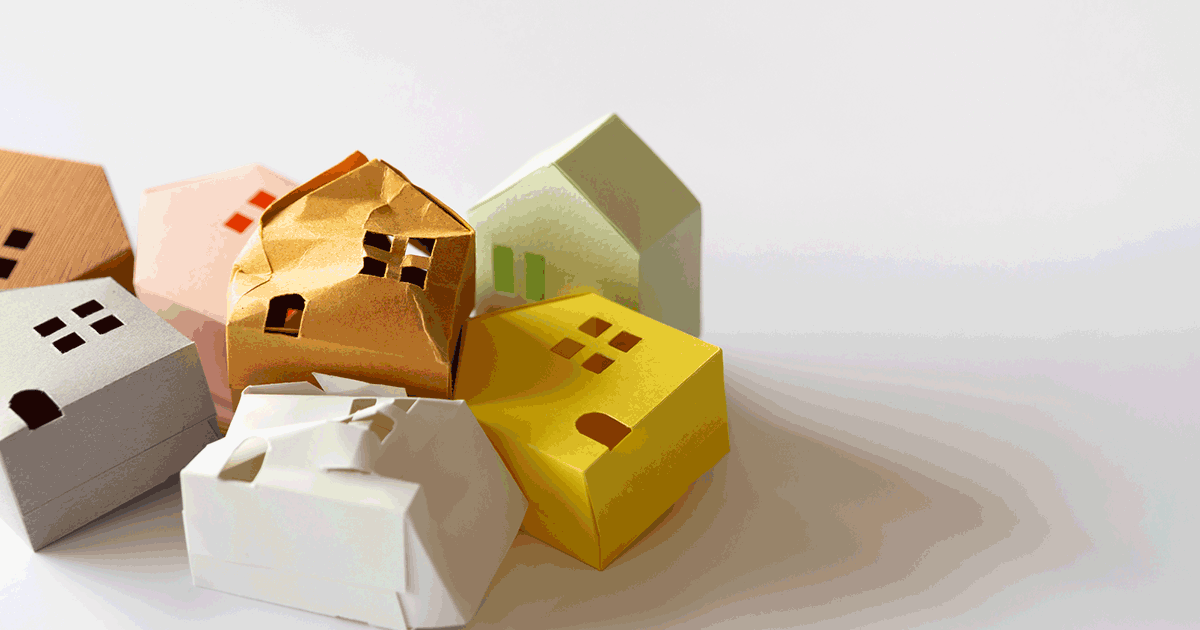目次
はじめに
「不動産を相続したけれど、売ることもできず、保有し続けるにも費用がかさむ……」
このような「負動産」問題に直面する方が急増しています。今後さらに深刻化すると予想されるため、できるだけ早めに対応を考えることが大切です。
本記事では、負動産を相続した際に取るべき選択肢や、処分方法を解説します。相続や不動産処分に悩んでいる方はもちろん、これから相続が発生する可能性がある方も参考にしてください。
第1章 負動産とは負の財産になっている不動産のこと
負動産とは、所有していることで、管理費や固定資産税などのコストがかさみ、価値を生み出すどころか経済的負担となっている不動産のことです。
かつては「土地は持っていれば価値が上がる」といわれた時代もありましたが、今や過去の話となっています。不動産市場は二極化が進み、価値が上がる資産と、負債と化す資産が明確に分かれている現状です。
特に、地方都市や過疎地域では、空き家や利用価値のない土地が増加し、売却も困難なケースが多発しています。よって「相続したはいいが手放したくても手放せない」といった状況に追い込まれる方も珍しくありません。
1-1 負動産の具体例
では、負動産と呼ばれる物件の具体例を見ていきましょう。
- 郊外の老朽化した空き家
- 再建築不可の土地
- 農業従事者がいなくなった田畑
- 商業施設から離れた立地の使われていないビル
- 極端に道路アクセスが悪い山林
- 災害リスクが高く再利用が困難なエリアの土地
負動産化すると、固定資産税の支払い義務があるにもかかわらず、収益化が見込めず、維持するだけでコストが膨らんでしまいます。
よって、所有者は大きな負担を強いられることになるでしょう。
1-2 負動産は2025年問題に挙げられている
2025年問題とは、団塊の世代が後期高齢者となることで、日本の社会全体にさまざまな影響が及ぶと懸念されている問題です。例えば、社会保障費の負担増、人手不足などが挙げられます。
不動産分野も2025年問題に挙げられており、相続による大量の物件流通が予想され、市場における供給過多が発生し、「売れない不動産」の増加が懸念されています。
管理が難しい負動産が増えると、空き家の深刻化にもつながるため、政府や自治体も空き家対策に乗り出しています。しかし、社会全体の問題として放置するのではなく、個人としても負動産の対策に取り組む必要があるでしょう。
第2章 負動産が問題となっている理由は?
負動産は社会問題となっており「売れない不動産」というだけでなく、様々な悪影響を発生させる可能性が懸念されています。
治安悪化や景観破壊、防災リスクの増大につながるといわれています。また、個人にとっても経済的な負担が増えるため、早めに負動産問題を対策する必要があるでしょう。
ここでは、個人の経済的な問題に焦点をあてて解説します。
2-1 維持費と管理が負担となる
空き家や使われていない土地であっても、定期的な草刈りや建物の補修、倒壊防止対策など、維持管理が必要です。「使用していないから」と放置すると、行政指導や罰則の対象となる可能性もあります。
特に、老朽化が進んだ建物は近隣住民に被害を及ぼすリスクが高く、法的責任を問われる恐れもあるでしょう。結果、維持管理を怠るわけにはいかず、多額のコストが発生してしまいます。
2-2 売却が難しい
売却活動をしようと考えても、負動産は不利です。買い手がつかず、大幅な値下げを余儀なくされるケースが多くあります。
さらに、リフォーム費用や解体費用が発生する場合は、売り手側が負担しなければならないこともあり、売却自体が赤字になる可能性もあります。
不動産会社によっては、取り扱いを拒否されることもあるでしょう。
2-3 固定資産税がかかる
たとえ利用していない不動産であっても、固定資産税や都市計画税は毎年課税されます。
特に、市区町村長から勧告を受け、特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置が解除されてしまいます。軽減措置の解除後は、税額が大幅に増加するため注意が必要です。
特定空き家は、以下の条件に該当する不動産を指します。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
引用:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置/国土交通省
年間数万円から数十万円単位の税金を負担し続けることは、家計にとって無視できない痛手となるでしょう。
2-4 配偶者や子供に負動産が相続される
相続によって、思いがけず「負動産」を引き継ぐケースは珍しくありません。
特に、相続人が複数いる場合、誰が引き取るかでもめたり、話がまとまらず処分が進まないといったトラブルに発展しがちです。
負動産問題は、自分一人では抱えきれず、結果として家族全体に負担をかけることになります。
自分の代で問題を先送りにしてしまえば、次の世代に大きな迷惑をかけることになりかねません。配偶者や子供に負動産を相続させないためにも、元気なうちから準備を進めておくことが大切です。
第3章 売れない負動産の処分方法
「売れない負動産を抱えてしまったら、どうすることもできないのだろうか……」
不安に感じる方も多いかもしれませんが、売却が困難な負動産であっても、処分する方法は存在します。
では、売れない負動産の処分方法を解説します。
3-1 隣地所有者へ譲渡する
現実的かつスムーズに進みやすい選択肢は、隣地の所有者に土地や建物を譲渡する方法です。
特に、土地の拡張や駐車場としての活用を希望している場合、交渉成立の可能性が期待できます。譲渡価格は市場価格よりも安くなることが一般的ですが、管理コストから解放されるメリットは大きいでしょう。
また、譲渡する際は、簡単な売買契約書や贈与契約書を取り交わすと後々のトラブルを防ぐことができるため、忘れずに行いましょう。
3-2 持分買取を利用する
共有名義の不動産を所有している場合、自分の持分のみを売却することが可能です。持分を売却すると、買取した人が代わりに不動産の名義人になることができます。
持分買取の専門業者を利用すれば、現金化できる可能性がありますが、持分だけでは実質的な利用が難しく、通常の売買に比べて価格はかなり低くなる傾向があります。
しかし、負の資産を手放してリスクを回避できる点では有効な手段といえるでしょう。
3-3 無償譲渡のマッチングサイトを活用する
インターネット上で、不動産を無償で譲渡したい方と、取得したい方をつなぐマッチングサイトが存在します。無償譲渡のマッチングサイトを活用することで、通常の売買では買い手が見つからない負動産でも、特定のニーズを持つ人に引き取ってもらえる可能性があります。
マッチングが成功したあとは、契約書を作成し、名義変更手続きを確実に行い、譲渡後のトラブルを防ぎましょう。専門家に依頼して進めると失敗がないため、おすすめです。
3-4 相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年4月に施行された相続土地国庫帰属制度を活用すれば、一定条件を満たす土地を国に引き取ってもらうことが可能です。
対象となる土地は、建物がない、汚染や崩落のリスクがないなど、厳しい条件をクリアした土地のみです。担保権や使用収益権が設定されている土地や、他人の利用が予定されている土地は引き取れないため注意しましょう。
審査には数か月かかることがあり、申請費用も土地一筆あたり14,000円支払う必要があります。
また、審査を通過し国による引き取りが正式に決まった場合は、「負担金」と呼ばれる費用の納付が必要です。負担金とは、国が引き取った土地に対し、将来的に発生する管理コストを前もって負担してもらうためのもので、土地の種類や面積、状態によって金額が異なります。
宅地であれば原則として土地一筆あたり20万円が標準とされていますが、山林や農地などではさらに高額になるケースもあります。
申請手数料と負担金を合わせると一定の費用はかかりますが、成功すれば負担から解放されるメリットは大きいでしょう。
3-5 自治体などに寄付をする
売れない負動産は、自治体や公共団体に不動産を寄付する方法もあります。
寄付が成立すれば、地域貢献にもつながり、社会的意義も高い取り組みとなるでしょう。
しかし、受け入れ基準は厳格で、簡単には引き取ってもらえないのが現状です。手続きには時間と労力がかかる点を理解しておきましょう。
3-6 相続放棄する
どうしても負動産を引き取るメリットがない場合、相続放棄をする選択肢もあります。ただし、相続放棄をすると、対象不動産だけではなく、すべての相続財産を放棄することになるため注意しましょう。
ほかに有利な財産がある場合は、相続放棄したことで後悔する可能性があるため、事前に財産全体を確認することが大切です。相続放棄の手続き後は、撤回ができないため慎重に進めなければなりません。
また、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるため、相続放棄を考えている場合は早めに行動しましょう。
第4章 負動産にならないための対策
負動産を所有しない、あるいは相続しないためには、事前の対策が欠かせません。日頃から資産管理の意識を高め、リスクがある場合は早めに行動に移すことが大切です。
では、負動産にならないための対策を解説します。
4-1 不動産の価値・リスクを把握する
所有する不動産がある場合は、定期的に市場価値やリスクを確認する習慣を持ちましょう。不動産会社などに相談し、現状を客観的に評価してもらうことが大切です。
特に、過疎地や災害リスクがあるエリアに所在する物件を所有している場合は注意が必要です。早めに価値を把握しておくことで、最適なタイミングでの売却や有効活用が可能になるでしょう。
4-2 価値のない不動産は所有し続けない
資産価値が下がり続ける不動産を所有し続けると、大きな負担を背負うことになります。
市場価値が著しく低下している場合は、早めに売却や処分を検討しましょう。場合によっては、多少の損失を受け入れてでも手放す方がよいケースもあります。
価値のない不動産を定期的に整理することで、将来のトラブル回避につながります。
4-3 相続が始まる前に家族会議をしておく
相続が発生する前に、不動産の扱いについて家族間で話し合いをしておきましょう。
誰がどの資産を引き継ぐか、どう活用するかを事前に明確にしておくことで、相続が発生した後のトラブルを防げます。また、必要に応じて遺言書の作成や、生前贈与の検討も視野に入れましょう。
家族全員が納得できる形を整えておくことが、円満な相続につながります。
4-4 共有名義は極力避けるか整理する
共有名義の不動産は、処分や管理が非常に難しくなります。できるだけ単独名義にしておくか、共有持分を整理しておくことが大切です。
早めに話し合いを行い、不動産の共有名義を回避することをおすすめします。例えば、換価分割や代償分割が有効です。
共有状態を放置すると、さらに二次的な相続が発生して売却や活用が進まなくなり、負動産化するリスクが高まります。
第5章 負動産を相続したあとの対処法
負動産を相続してしまった場合でも、適切な対応を取ることで損害を最小限に抑えることが可能です。できるだけ早めに行動して、負動産問題を解決しましょう。
では、負動産を相続したあとの対処法を解説します。
5-1 専門家に相談して価値を判断する
素人判断では正確な価値評価やリスク把握が難しいため、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
相続放棄すべきか迷ったら、司法書士や不動産鑑定士、税理士などの専門家に相談しましょう。不動産の市場動向や今後のリスクなど、客観的な意見をもらうことで、判断ミスを防げます。
専門家を選ぶ際は、地域の事情に詳しい人物を選ぶとより実践的なアドバイスが得ることができます。
5-2 売却や譲渡を検討する
売却できそうな物件であれば、速やかに売却を目指しましょう。不動産会社に相談して、売却できる可能性があるか、あるいは賃貸活用できるかを検討しましょう。
ただし、売却活動に時間がかかる場合もあるため、複数の不動産会社へ査定依頼を出し、条件の良い方法を選択することがポイントです。
難しい場合でも、無償譲渡マッチングサイトや相続土地国庫帰属制度の活用など、可能な限り負担を軽減する方法を探りましょう。
5-3 所有を続ける場合は費用を明確化させる
どうしても所有を続ける必要がある場合は、維持管理にかかる費用を明確にし、資金計画を立てましょう。
無計画に所有し続けると、思わぬ負担が重くのしかかるため、固定資産税、修繕費、管理費用などを見積もり、長期的な視点でコスト管理を徹底する必要があります。
また、空き家対策で最低限の修繕や清掃を行い、資産価値を保つ努力も欠かせません。
5-4 相続放棄できる状況か確認する
負動産を相続した場合でも、条件次第では相続放棄を選択できる可能性があります。
家庭裁判所への申し立ては、相続開始を知ってから3か月以内と期限があるため、早急に財産状況を整理し、放棄すべきか判断しましょう。相続放棄を選ぶ場合は、他の相続人に押しつけるような形になる場合は、それらの相続人に配慮した対応をした方がいいでしょう。
自己判断が難しい場合は、専門家のアドバイスを受けながら判断するとよいでしょう。
まとめ:負動産も相続の対象に!困ったら専門家に相談しよう
負動産は、放置していても自然に解決する問題ではありません。むしろ、放置すればするほど、税金や管理費用といった負担が膨れ上がってしまいます。
負動産を相続した、あるいは今後相続する可能性がある場合は、早めに対策することが大切です。困ったときは一人で悩まず、専門家に相談して解決策を見出しましょう。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。