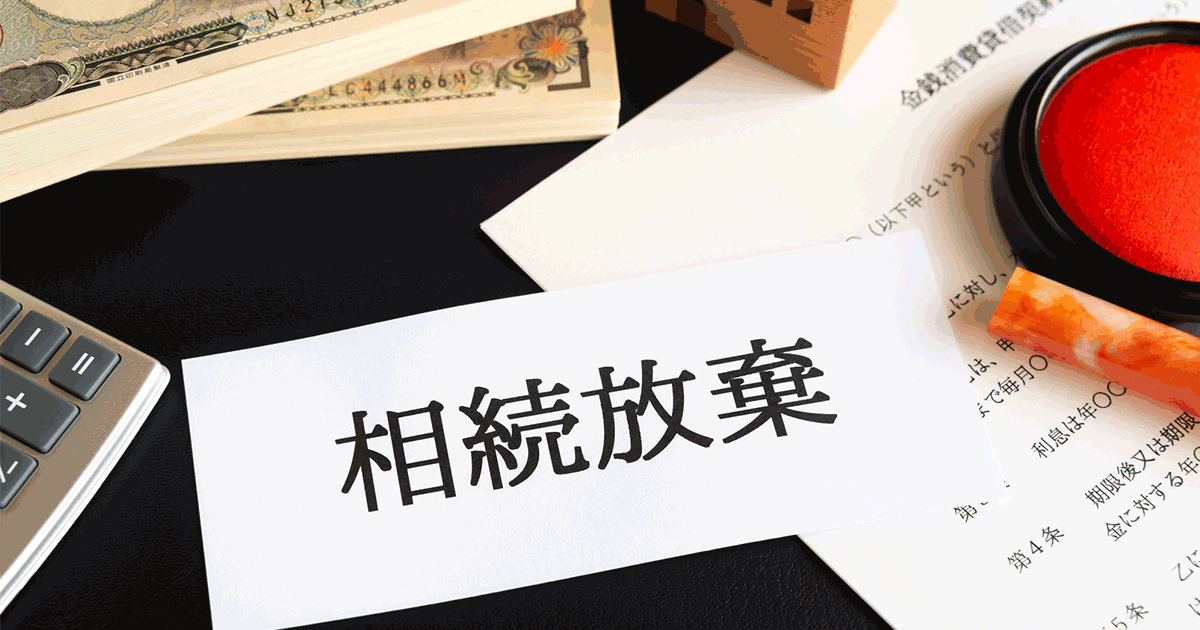目次
はじめに
「親が遺した古い実家は相続放棄すればもう関係ない」
そんなふうに思っていたのに、放棄しても管理義務が残ると聞いて不安になっていませんか?
相続放棄をしたとしても、一定の条件下では不動産の管理や保存に関する義務が残ることがあります。知らずに放置してしまうと、思わぬトラブルや費用の負担につながる可能性もあるのです。
この記事では、相続放棄の基本から不動産に関わる具体的な手続き、放棄後に残る義務、さらに売却・賃貸といった他の選択肢まで、専門知識がなくても理解できるようにやさしく解説します。
1章 相続放棄の基本知識
相続放棄は、遺産を一切受け取らないという意思表示です。
特に不動産が含まれる相続の場合、後々の管理や税金の負担を避ける目的で放棄を検討される方が増えています。
しかし、相続放棄はすれば終わりという簡単なものではありません。期限や手続きの流れをきちんと把握しないと、思わぬトラブルに発展する恐れもあります。
ここでは、相続放棄の基本的な知識として、まずはその期限と流れについて解説します。
1-1 相続放棄できる期限と手続きの流れ
相続放棄には、手続きの期限があります。
原則として、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄を届け出る必要があります。この期間を過ぎると、法律上は相続を承認したと見なされます。届出して相続放棄が正式に受理されると、届出した人は、法律上初めから相続人でなかったことになります。
以下が、一般的な相続放棄の手続きの流れです。
- 相続財産を調査して把握する
- 相続人の間で意思確認する
- 戸籍謄本などの必要書類を集めて相続放棄申述書を作成する
- 家庭裁判所への書類を提出する
- 家庭裁判所からの受理通知を確認する
はじめに、被相続人の不動産や預貯金、借金などを正確に把握します。その上で相続放棄をするかどうかを判断しましょう。相続放棄は自分一人の判断で行うことができますが、できれば他の相続人にも意思を共有しておいた方がいいでしょう。
相続放棄することを決めたら、戸籍謄本などを取得し、「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所へ提出します。
書類に不備がなく、正しく受理されたら家庭裁判所から通知が届きます。
こうした流れをスムーズに進めるためには、早めの情報収集と準備が非常に重要です。迷ったら一人で抱え込まず、専門家に相談するのも一つの方法です。
1-2 相続放棄に必要な書類と提出先
相続放棄を行うには、所定の書類をそろえて家庭裁判所へ提出する必要があります。
基本的に必要な書類については以下のとおりです。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロード可能)
- 被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票(あるいは戸籍附票)
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 収入印紙 800円分
- 郵便切手
被相続人の戸籍謄本は、被相続人と相続人の関係がわかる範囲のものが必要となります。親や兄弟が相続人となるときは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を求められます。また、申述人が被相続人の子や兄弟姉妹であることを証明するために自分の戸籍謄本も必要です。
申述人が被相続人の配偶者や子供ではなく、兄弟姉妹や親、甥・姪の場合は、先順位の相続人がいないことを証明する戸籍謄本も必要になります。
これらの書類をそろえたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
郵送でも提出できますが、不備があると再提出になる可能性もあるため、できれば送る前に電話などで家庭裁判所へ直接確認しておくと安心です。
1-3 相続放棄するときの注意点
相続放棄には、いくつか注意すべきポイントがあります。相続放棄するまでにはさまざまな制約があるほか、放棄したことによる影響が他の親族へ及ぶこともあるためです。
ここでは、特に注意したいことを詳しく解説します。
1-3-1 「不動産だけ」相続放棄はできない
たとえば、家などの不動産は不要なので放棄して、預金や貴金属だけ相続するといったことはできません。相続放棄は相続財産のすべてを対象とするもので、一部だけを選んで放棄することは認められていません。
つまり、不動産を相続放棄するなら、預金や貴重品、借金なども含めて一切を放棄することになります。
部分的に選べないからこそ、不動産の価値や負債の有無などをよく調べてから判断することが大切なのです。
1-3-2 相続放棄すると他の親族へ権利が移る
相続放棄をすると、次順位の相続人に権利や義務が移ることがあります。
たとえば、申述人が子の場合、子の全員が相続放棄をすれば次に被相続人の親や兄弟姉妹や甥・姪などが相続人になる可能性があります。ただし、相続権が移ったという情報は家庭裁判所から当該の人に自動で通知されるわけではありません。
知らないうちに負担を背負わせてしまうことのないよう、放棄の手続きをする前に親族間でしっかり話し合っておくことが大切です。
1-3-3 放棄前に「相続した」とみなされる行為をしないように注意する
相続放棄をするつもりでも、受理される前の行動次第で相続を受け入れたとみなされてしまうケースがあります。
これは単純承認と呼ばれ、それ以降は相続放棄が認められなくなる可能性があります。
たとえば、以下のような行為に注意しましょう。
- 不動産の名義変更をした
- 被相続人の口座から借金や税金を支払った
- 遺品を売却・処分した
意図せず単純承認したとしても、以後は借金の返済義務も含めて相続を引き受けたことになります。
放棄の意思がある場合は、手続きを完了するまで慎重に行動しましょう。
2章 【注意】不動産を相続放棄しても住んでいれば保存義務が残る
相続放棄をしたら家のことは関係なくなると思うかもしれませんが、実際にはそう簡単ではありません。放棄すればすべて終わりではなく、放棄した後にどう備えるかが重要なのです。
2023年の民法改正により、相続放棄後であっても保存義務が残るケースがあることが明確にされました。以前は「管理義務」と表現されていましたが、法改正を経て、より限定的な「保存義務」に整理されています。
特に、相続放棄をしても家に住み続けていると、その間は最低限の管理責任(保存義務)が発生します。
この章では、相続放棄後にどのような義務が残るのか、いつまでその義務が続くのか、また管理にかかる費用やリスクについて具体的に解説していきます。
2-1 相続放棄後に保存義務が残るのはいつまでか
相続放棄をしても、すぐに不動産の管理責任から完全に解放されるわけではありません。
2023年の民法改正により、現に占有されていた相続人は管理義務を負うと明文化されました。これは、不動産が放置されたことで第三者に被害が出ないようにするための最低限の責任です。
この保存義務は、他の相続人に財産が引き継がれるまで、あるいは相続財産管理人が選任されて管理を引き受けるまで継続します。
もし全員が相続放棄した場合、以下のような流れになります。
- 相続人が全員相続を放棄する
- 相続財産は誰も管理しない状態になる
- 利害関係人や検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任申立てを行う
- 裁判所が相続財産管理人を選任し、その人に管理権限が移る
この手続きには、予納金として数十万円の費用がかかる場合もあります。手間も時間もかかるため、実際には選任までに時間が空くことも多く、その間は相続放棄をした人に一時的な保存義務が残ることになるのです。
不動産のトラブルを未然に防ぐためにも、放棄後の流れを把握しておきましょう。
2-1-1 不動産の管理費・解体費の目安
相続放棄をしても、管理人が選任されるまでは不動産の保存義務が残り、管理や維持に費用がかかります。
自分で管理する場合は草刈りや清掃、害虫・害獣対策、火災保険、修繕費などが発生し、固定資産税などの税金も含めると年間約35万円~50万円程度必要です。かといって放置すれば、近隣トラブルや責任問題につながる恐れがあります。
物件の管理を続けるのが難しい場合は解体を検討することになりますが、例えば木造住宅の場合には解体費に120万〜250万円かかることもあり、大きな出費が伴います。
なお、解体費は構造や面積によって大きく変わり、木造よりも鉄骨造の方が費用は高額です。
相続放棄した後も、このように想定外の負担があるかもしれないと認識しておきましょう。
2-1-2 管理義務を怠った場合のリスク
相続放棄をしても、相続財産管理人が決まるまでは不動産の保存義務が残る可能性があります。
この期間に適切な管理を怠ると、倒壊や火災による近隣被害、不法投棄、犯罪利用など、深刻なトラブルや賠償責任につながる恐れもあるので注意が必要です。
放棄したからといって無関係とはいえず、管理人が選任されるまでのあいだは、最低限の保存・管理を行う責任があることを理解しておかなければなりません。
3章 不動産を相続放棄するメリット・デメリット
古い家や使う予定のない土地などを相続してしまうと、管理や税金の問題が発生することもあるため、放棄してしまった方が楽かもと考える方も多いでしょう。
しかし、相続放棄には明確なメリットがある一方で、思わぬデメリットも存在します。後悔しない判断をするためには、両面から冷静に検討することが大切です。
ここでは、不動産に限定した相続放棄のメリット・デメリットを具体的にご紹介します。
3-1 メリット
不動産を相続放棄する最大のメリットは、維持管理や税金などの経済的負担から解放されることです。
たとえば、相続する不動産が空き家の場合、以下のような費用やリスクを避けることができます。
- 固定資産税の支払い義務がなくなる
- 老朽化による修繕や管理の手間を回避できる
- 不動産の価値が不明・低い場合のリスクを避けられる
売却も難しく、費用倒れになる物件を抱える必要がなくなります。所有者でなくなるため、原則として固定資産税などの税金を支払う義務も発生しません。
さらに、空き家放置による近隣トラブルの心配もなくなります。
相続した不動産を自分が使う予定がないうえに管理も難しい場合には、相続放棄は前向きな選択肢の一つです。
3-2 デメリット
一方で、相続放棄を選ぶことには大きなデメリットもあります。
- 他の財産もすべて放棄しなければならない
- 不動産の将来的な価値を失う可能性がある
- 親族との関係に影響が出ることもある
不動産以外に現金や預金、株式などの資産があっても、相続放棄すればそれらも一切受け取れません。
さらに、不動産には、今は価値がないように見えても将来使える可能性があるケースもあります。
たとえば、相続した土地が開発予定地になって価値が上がり、上がったタイミングで売却して利益が出るようになっても、放棄していればその恩恵は一切受け取れません。放棄を決める前に、一度その物件の価値を調べてみるのがおすすめです。
また、自分が相続放棄することで、次順位の相続人に責任が移って迷惑をかけてしまう場合もあることにも注意しましょう。
4章 不動産を相続放棄する以外に選べる4つの方法
相続放棄は確かに有効な選択肢の一つですが、手放す前に他の方法はないかと考えてみることも大切です。実際、不動産には活用の道が残されていることも多く、うまく運用すれば収入や資産としての価値につなげられるケースもあります。
ただし、相続放棄は相続してから3か月以内に手続きしなければならないので、早めの判断が必要です。
ここでは、相続放棄をせずに不動産を扱うための4つの選択肢について、メリット・デメリットを含めてわかりやすく解説します。
4-1 売却する
使わない家を手放すなら、売却を考えてみても良いでしょう。たとえ古い家でも、リノベーション需要や立地条件で、意外と買い手が見つかることがあります。
売却方法としては、自治体が運営する空き家バンクの活用や、不動産会社への依頼があります。空き家バンクでは無償譲渡になることもありますが、不動産会社なら適正価格での売却が期待できます。
老朽化が激しい場合は、解体後に土地として売る選択もあり、事前の相談や査定がカギになります。
4-2 賃貸に活用する
相続した不動産に今すぐ住む予定がない場合は、貸すといった活用方法があります。立地条件が良く再利用できる物件なら、リフォームを施して賃貸住宅として収益化が可能です。
賃貸に出せば家賃収入で固定資産税や管理費を補えるほか、空き家による老朽化や防犯面のリスクも軽減できます。また、将来的に自分や家族が住む選択肢も残せるのもメリットです。
一方で、賃貸活用にはリフォーム費用や管理の手間・コスト、空室リスク、入居中の修繕対応、将来の売却制限といったデメリットもあります。始める前に物件の状態や地域の需要を見極め、不動産会社に相談するのがおすすめです。
物件を自分で管理するのが難しい場合は、管理会社に委託する方法もあります。月額数千円~1.5万円ほどで巡回や清掃、修繕手配などを任せられるので、遠方に住んでいる方や忙しい方にはおすすめです。
ただし、契約する際には委託内容の範囲、手数料相場、契約条件、実績を確認し、信頼できる業者を選びましょう。
4-3 相続土地国庫帰属制度を利用する
売れない・貸せないが管理し続けるのも難しい、といった不動産に悩んだとき、最後の手段として検討できるのが相続土地国庫帰属制度です。
相続した土地を手放したいとき、一定の条件を満たせば所有権を国に返還することができます。これは相続放棄とは異なり、相続した後に手放すことができる制度です。
利用するための条件は以下の通りです。
- 建物が建っていないこと(更地であること)
- 境界が明確で、争いがないこと
- 土壌汚染などがないこと
- 管理に過度な費用がかからない土地であること
参考:相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」/政府広報オンライン
これらの条件を満たしていなければ、申請は受理されません。また、申請の際には10年分の管理費に相当する負担金として原則20万円程度の納付も必要になります。
注意点として、建物が残っている場合は解体してから申請する必要があります。また、審査には時間がかかり、書類不備があると却下される可能性もあるので注意が必要です。
さらに、利用できるのは土地のみであり、建物には対応していません。
利用までの条件が厳しい制度ではありますが、管理し続ける負担を考えれば検討する余地は十分にあります。
4-4 寄付・贈与する
不動産を手放す手段としては寄付や贈与もあります。
しかし、自治体への寄付は、利用目的の制限や管理費用の問題、境界や土壌汚染などのリスクを理由に、断られるケースがほとんどです。
寄付や贈与するなら親族や知人、企業への贈与のほうが現実的ですが、贈与税や譲渡所得税が発生する可能性があり、受け取る側の合意や負担も確認しましょう。
まとめ:相続した不動産を放棄するか迷ったときは専門家に相談を
不動産の相続放棄は、すべてを手放して解放されるように思えますが、実際には保存義務や費用が残ることもあります。また、他の財産も一切受け取れなくなるため、本当に放棄が最善か見極めが必要です。
不動産を相続放棄してしまう前に売却・賃貸・国庫帰属・寄付といった他の手段も検討する余地はあります。状況によっては、放棄より有利な選択肢が見つかる可能性もあるでしょう。
もしも不動産を相続放棄するのに不安があるなら、早めに専門家へ相談しましょう。さまざまな選択肢から後悔のない判断ができるはずです。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。