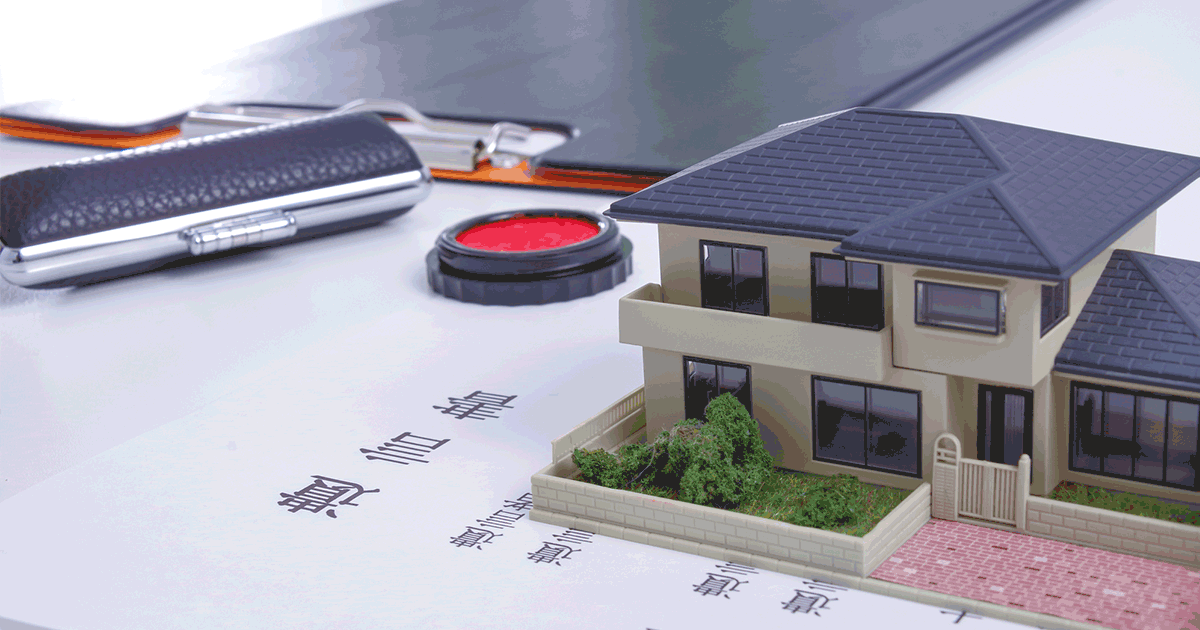目次
はじめに
不動産は、相続税の負担が大きいため、相続対策には節税効果を狙った計画が大切です。
また、不動産の相続は節税対策だけではなく、相続人のトラブル防止も意識する必要があります。どちらか一方だけでは不十分なため、不動産の相続対策は早めに行わなければなりません。
本記事では、親族間のトラブル回避と節税のパートに分けて、不動産の相続対策を解説します。不動産の相続で失敗しないために、元気なうちから相続対策を始めましょう。
第1章 不動産の相続対策が必要な理由とは?
不動産は、相続対策をしないとトラブルや予想以上の税負担に悩まされることになります。不動産は価値が高い分、相続における影響力も大きく、計画性のない相続は資産を大きく減らす原因になりかねません。
では、不動産の相続対策が必要な理由を解説します。
1-1 分けにくい資産だから
不動産は、現金のように簡単に分けることができません。
一つの土地や建物を複数人で相続するといったんは共有になりますが、その場合、不動産の売却や活用、修繕に他の相続人(全員または過半数)の同意が必要となるため、管理面の負担が増します。
そのため、遺産分割によって相続人の誰かの単独所有にした方がよいでしょう。しかし、遺産分割で相続トラブルが起こった場合、単独所有が難しくなるため、生前より相続対策をしておくことをおすすめします。
特に、親族間で「この家に住み続けたい」と考えている方がいれば、トラブルに発展し、関係性が悪化することもあるでしょう。
1-2 評価が難しくトラブルになりやすいから
不動産の評価は、路線価や固定資産税評価額、市場価格など複数の基準があり、それぞれ数値が異なります。また、不動産の利用状況や将来性、立地によっても価値は変動するため、単純な数字だけでは測れない部分も多くあります。
なお、遺産分割では、不動産を時価(実勢価格)で評価することが原則です。後々のトラブル防止をするためにも、専門家による複数の評価を取り、納得感を持たせるようにしましょう。
1-3 節税・節約に活用できる可能性があるから
不動産は、節税の観点で有効な資産です。現金で保有しているよりも、不動産に変えておくことで、相続税の負担を減らすことが可能になります。
特例制度や控除も多数存在しており、活用することで大きな節税効果を得られます。ただし、節税対策には条件やリスクがあるため、メリット・デメリットを正しく理解して最適な方法を選びましょう。
第2章 不動産を希望の人物に相続させるための方法
不動産を希望の人物に確実に相続させるには、生前の対策が欠かせません。生前に適切な対策をすることで、遺産分割協議を円滑に進めることができ、家族間のトラブルを防止できます。
希望する相続人が不動産を確実に引き継げるよう、計画的に行動を起こしましょう。
では、不動産を希望の人物に相続させるための方法を解説します。
2-1 遺言書を作成して意志を明確にする
基本的な対策は、公正証書遺言などの法的効力のある遺言書を作成することです。
誰にどの不動産を相続させたいかを明示することで、争いを防ぐことができます。特に、家族構成が複雑な場合や特定の子に財産を集中させたい場合には必須です。
また、遺言書の作成をする際は、遺留分にも配慮しなければなりません。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる取り分のことです。遺留分を侵害すると争いの原因になるため、専門家に相談しながら、遺言の内容を慎重に決める必要があります。
2-2 生前贈与を活用する
生前贈与を活用することで、相続時のトラブルを回避することが可能です。ただし、贈与税の課税対象になるため、年間110万円の非課税枠や相続時精算課税制度を利用して節税対策をする必要があります。
生前贈与は贈与のタイミングも大切です。亡くなる3年以内の贈与は相続財産に加算され、相続税の対象となるため、早めに計画を立てなくてはなりません。
また、不動産贈与の場合は、登記手続きや税務申告も必要です。スムーズな手続きをするためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
2-3 家族信託を利用する
家族信託とは、不動産などの財産を信頼できる家族に託し、管理や処分を任せる制度です。
家族信託を活用することで、不動産の凍結リスクを回避でき、相続人の意向に沿った資産管理が可能となります。凍結リスクとは、所有者が認知症を発症したり判断能力を失ったりした場合に、不動産の売却や管理、修繕などの意思決定が難しいことから、不動産の活用が一切できなくなる状態のことです。
家族信託をあらかじめ設定しておけば、信頼できる家族に管理や処分の権限を託すことができ、不動産の凍結状態を未然に防ぐことができます。特に、複数の不動産を持っている場合や、相続人が決まっていない場合に有効です。
また、認知症などによって判断能力が低下した場合でも、スムーズな資産運用や相続が可能になり、相続税の節税につながる場合があります。
2-4 売却や買い替えで不動産を整理する
複数ある不動産を売却したり、扱いやすい物件に買い替えたりする方法も有効です。
分割しにくい資産を整理しておくことで、トラブルを避けることができ、納税資金の確保や節税につながるケースがあります。また、老朽化した不動産や収益性の低い物件は、早期に売却することで、資産が目減りするリスクを防ぐことができます。
不動産を整理する際は売却だけではなく、資産全体の最適化を目指して計画的に行いましょう。
第3章 相続トラブルを未然に防ぐための方法
相続トラブルを未然に防ぐためには、事前の準備と家族間のコミュニケーションが不可欠です。不動産を含む財産は高額であるため、トラブルを引き起こすリスクが高いといえます。
信頼できる専門家と連携し、複数の選択肢を比較検討しながら最適な方法を選びましょう。
では、相続トラブルを未然に防ぐための方法を解説します。
3-1 家族全体での話し合いの場を作る
相続対策は一人で進めるのではなく、家族全体で共有することが大切です。
家族の集まりを定期的に設けて、相続に対する考え方をすり合わせておきましょう。意見の違いを事前に確認し、将来の方針を明確にしておくことで、相続開始後のトラブルを防ぐことができます。
可能であれば、第三者である専門家を交えた家族会議を行い、相続に関する情報共有と意思確認をする機会を作るとよいでしょう。
3-2 信頼できる専門家に相談する
司法書士や税理士、不動産鑑定士など専門家の意見を取り入れることで、適切な相続対策ができます。最新の税制改正や法律の動向を踏まえたアドバイスが得られるため、トラブル防止につながるでしょう。
また、専門家は感情に左右されず、冷静な視点でアドバイスをしてくれるため、家族間の意見の対立が激しい場合も中立的な立場でアドバイスしてくれます。
早い段階から相談を開始し、長期的なサポートを受ける体制を整えることが大切です。
3-3 生前対策を早めにする
生前対策は、早ければ早いほど効果的です。資産の棚卸し、遺言書の作成、信託契約の締結など多くの手続きがありますが、判断能力が必要な手続きなので、判断能力が衰える前に行動を起こしましょう。
元気なうちに対策を行うことで、自分の意思を最大限に反映した相続プランが可能となり、万が一の事態にも備えることができるでしょう。
生前対策は「まだ早い」と思わず、できるだけ早めに着手することが大切です。
第4章 不動産を活用した相続税対策の方法
不動産は、適切に管理・運用することで評価額を抑えられるため、相続財産全体の課税対象額を大きく引き下げることが可能です。制度や特例を上手に活用するためには、少しずつ計画的に進めることが大切です。
では、不動産を活用した相続税対策の方法を解説します。
4-1 現金を不動産に変えておく
現金を不動産に変えることで、財産評価額を抑えることができます。
現金は額面がそのまま財産評価額となりますが、不動産に変えることで財産評価額が下がります。また、賃貸不動産の場合、さらに財産評価額を下げることが可能です。
例えば、以下のようなシミュレーションをチェックしましょう。
5,000万円の現金を賃貸用不動産に転換した場合のシミュレーション
| 項目 | 現金保有の場合 | 賃貸不動産に転換した場合 |
|---|---|---|
| 表面価格(購入額) | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 相続税評価額 | 5,000万円(100%) | 約3,000万円(約60%に圧縮) |
| 想定年間家賃収入 | 0円 | 約250万円(利回り5%想定) |
このように、現金をそのまま持っているよりも、賃貸不動産に転換することで、相続税評価額を抑えられるだけではなく、生活資金を確保することができます。
ただし、不動産購入をする際は、収益性や管理コストなどを検討し、慎重に進めることが大切です。
4-2 小規模宅地等の特例を利用する
被相続人の居住用や事業用の土地は、「小規模宅地等の特例」を活用することで、最大80%の評価減が可能となります。現金で相続する場合と比較し、非常に大きな節税効果があり、多くの相続案件で利用されています。
ただし、特例の対象となる物件は、居住の継続や事業の継続などの条件があるため注意が必要です。
特例を確実に受けるためには、事前のシミュレーションと専門家との連携が欠かせません。特例の適用漏れがないよう、専門家と一緒に進めることをおすすめします。
4-3 賃貸経営をして評価額を下げる
賃貸物件は「借家権割合」が適用され、節税には非常に有効です。借家権割合とは、賃貸物件や土地の相続税評価額を計算する際に差し引かれる割合です。
借家権割合は、全国一律で30%と定められており、相続税を減額する効果が得られます。成功すれば、節税と資産形成の両方を達成できる有効な戦略となるでしょう。
ただし、空室リスクや管理コストの発生があるため、慎重な物件選びや賃貸管理の体制を整えておくことが大切です。
4-4 土地を売却して節税効果の高い物件を購入する
収益性や財産評価額の観点から不利な土地を売却し、賃貸アパートやマンションなどの節税効果の高い不動産に買い替えることで、相続税の負担を軽減できます。
特に、利用予定のない土地や管理が困難な土地は、早期に売却してより収益性の高い資産に組み替えることが有効です。最適なタイミングで売却や再投資をして、戦略的に資産を入れ替えましょう。
第5章 相続対策で失敗したありがちなケースとは?
相続は、ただ資産を移転するだけではなく、家族の関係性や人生設計に大きな影響を与える手続きです。相続対策を万全に行ったつもりでも、失敗してしまうケースは珍しくありません。
では、相続対策で失敗したありがちなケースを解説します。
5-1 遺言書を作ったのに揉めたケース
遺言書があっても、内容が曖昧だったり公正証書ではない場合、遺言書に疑問が残り、相続人の間で争いになるケースがあります。また、一人の相続人に全財産を相続させるなど、遺言書の内容が現実的でなかった場合も、実際の運用で問題が発生するでしょう。
遺言作成時は、法的効力を高めるだけではなく、相続発生後の具体的な運用まで見越して設計することが大切です。専門家に確認しながら遺言書を作成し、第三者による遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
5-2 生前贈与が逆効果だったケース
生前贈与は、節税効果がありますが「3年ルール」により、亡くなる前3~7年以内の贈与は相続税の課税対象になります。3年(7年)ルールを知らずに贈与を繰り返し、節税効果がなくなったケースも珍しくありません。
また、贈与した資産が評価額の高い不動産であった場合、贈与税の負担が重くなり、生活資金に支障をきたす恐れもあります。
生前贈与を行う場合は、税理士などの専門家に相談し、計画的に進めることが大切です。
5-3 節税やトラブル回避に偏り過ぎた対策をしたケース
節税ばかりを優先して運用が難しい不動産投資をしたり、逆に感情を重視して合理性を欠いた資産分配をしたりすると、結果的にトラブルになる原因になります。
例えば、無理に賃貸物件を増やして相続税評価を下げたものの、空室リスクや管理負担が重くなり、家族の資産運用に支障をきたすケースも見られます。
一方、感情を優先して不動産を無理に単独相続させた結果、納税資金不足に陥ることもあるでしょう。
相続対策は、節税、資産維持、家族関係、それぞれのバランスを考えた戦略を立てることが欠かせません。納得のいく選択をするためにも、専門家のアドバイスを取り入れながら丁寧に進めましょう。
5-4 専門家に相談せず個人判断で動いたケース
税制や法律の知識が不十分なまま個人判断で対策を進めた結果、必要な手続きを漏らしたり、誤解により不利な条件で相続が進んでしまうケースは多く見られます。
特に、不動産相続は、税務だけでなく登記や契約実務も絡んでくるため、複合的な専門知識が求められます。
相続や贈与に関する税制は頻繁に改正されており、数年前の知識がすでに通用しないことも珍しくありません。そのため、正しいと思って進めた内容が、実は最新の制度に反していたケースも起こり得ます。
個人で対応しきれない問題が発生しやすいため、最新の法律や税制に詳しい専門家に依頼することが大切です。専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑え、スムーズな相続が実現できます。
まとめ:不動産の相続対策は戦略的に動くことが大切!
不動産の相続は複雑であり、放置すればするほど問題が大きくなります。節税対策を含め、早めの準備が相続トラブルの防止にも直結します。
また、相続対策は一度立てたら終わりではなく、ライフステージや税制改正に応じて適宜見直しをすることも大切です。節税だけに偏ることなく、家族の意向や資産の特性を踏まえたうえで、バランスの取れた相続プランを考えましょう。
「住まいの賢者」では、相続を得意とする司法書士と提携し、相続不動産の調査から登記、売却、活用までをワンストップで支援するサービスを提供しています。
初回相談・査定は無料で行っており、売却先のマッチングや税理士との連携も可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。