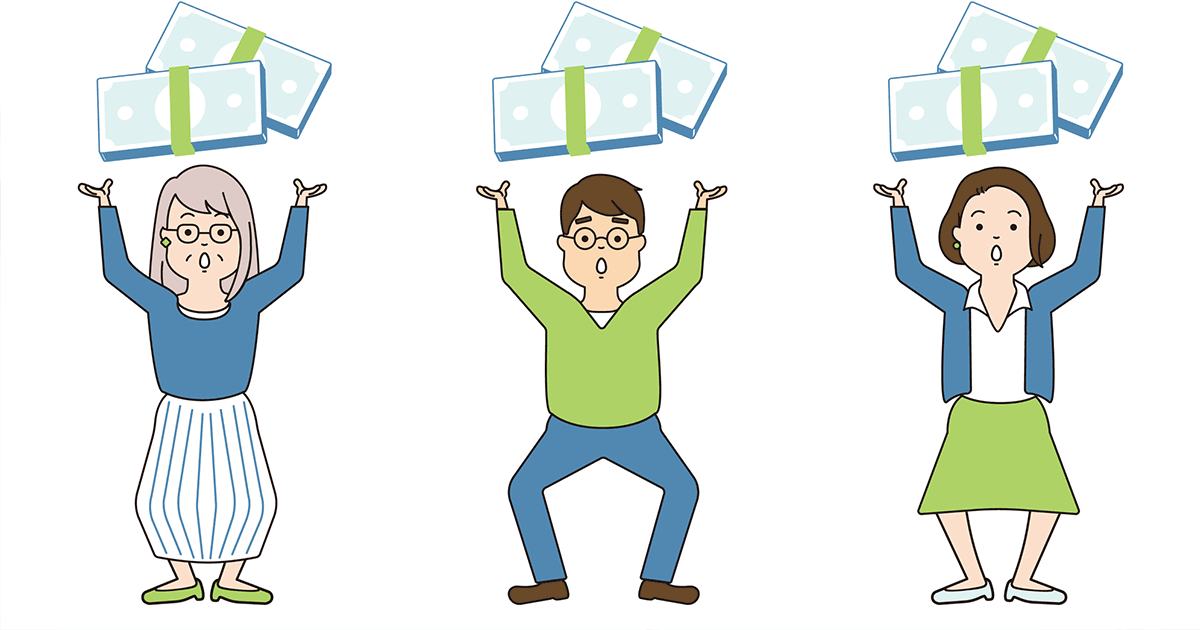目次
はじめに
相続人が複数いる場合、不動産などの遺産をどのように分けるかは大きな悩みの一つです。特に不動産は、現金のように簡単に分割できず、相続人同士の話し合いが長引いたり、トラブルに発展したりすることも少なくありません。
こうした状況で効果的なのが、不動産を売却して得た金銭を分配する換価分割です。この記事では、換価分割の基本的な仕組みや選ばれる理由、メリット・デメリット、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。相続方法でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
第1章 換価分割とは?基本の仕組みを再確認
相続では、遺産の分け方によって相続人間の対立が生じやすく、中でも不動産は分割が難しい財産の代表例です。相続財産の分け方には、以下のような方法があります。
| 相続方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物分割 | 遺産を現物のまま分ける方法(例:自宅は長男、預金は次男が取得) |
| 代償分割 | 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法 |
| 共有分割 | 相続人全員で不動産を共有名義とする方法 |
| 換価分割 | 遺産を売却し、その代金を相続人で分配する方法 |
現物分割は公平な分け方が難しく、代償分割では十分な現金を用意できない場合があります。また、共有分割は一見平等に見えても、管理や売却に関して相続人で意見が分かれ、将来的なトラブルに繋がりやすい点が課題です。
トラブルに発展しやすい不動産を伴う相続時に効果的なのが換価分割です。ここでは、換価分割の基本的な仕組みと、どのようなケースで選ばれやすいのかについて解説します。
1-1 換価分割の概要
換価分割とは、不動産などの現物を相続人がそのまま取得するのではなく、売却して現金化したうえで、売却代金を相続人で分配する方法を指します。
例えば、相続財産に含まれる不動産を3,000万円で売却し、相続人が3人いた場合には、1人あたり1,000万円ずつ分配することが可能です。ただし、実際の配分は法定相続分や他の財産の取得状況などによって変わるため、遺産分割協議によって分配内容を決めておく必要があります。
1-2 なぜ換価分割が選ばれるのか?
不動産は現金のように等分しづらいため、相続人の人数や状況によっては公平な分配が難しくなります。また、特定の相続人が不動産を相続し、代わりに他の相続人へ金銭を支払う代償分割は、相続人に資金力がなければ現実的な選択とは言えません。
一方、換価分割であれば、不動産を売却して現金化することで、公平な分配を実現しやすくなります。加えて、納税資金の確保や将来的な管理負担の軽減といった点でも効果的でしょう。そんな換価分割が適しているのは、以下のようなケースです。
- 公平に相続したい
- 誰も不動産を相続したくない
- 相続税の納税資金を確保したい
- 不動産を複数人で共有したくない、共有による将来のトラブルを避けたい
第2章 換価分割を選択する4つのメリット
換価分割を選択するメリットは以下の通りです。
- 公平に遺産を分割できる
- 代償金を用意する必要がない
- 納税資金を確保できる
- 不動産の評価を巡るトラブルを回避できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①公平に遺産を分割できる
不動産を現物のまま分けようとすると、土地や建物の価値に差が生まれ、不公平になってしまいます。例えば兄が母屋、妹が離れといった分け方では、資産価値や利便性に大きな差が生まれる場合もあります。
その点、換価分割では不動産を売却して現金に換えるため、遺産を公平に分割して相続することが可能です。
②代償金を用意する必要がない
代償分割では、特定の相続人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う必要があります。しかし、実際には不動産を取得したい相続人がいても、代償金を一括で用意するのが難しいケースは少なくありません。
一方で、換価分割であれば、不動産を売却して得た現金をそのまま分けるだけなので、代償金を用意する必要がありません。不動産を売却して得た現金をそのまま分けるだけなので、代償金という形で他の相続人にお金を支払う必要がなく、金銭的な負担が偏りにくいのが特徴です。
③納税資金を確保できる
相続税は、相続の発生から原則10ヶ月以内に現金で納付する必要があります。しかし、相続財産の多くが不動産のような現物資産に偏っている場合、手元に現金がほとんどないまま納税期限を迎えてしまうケースが少なくありません。
一方で、換価分割なら不動産を現物のまま相続するのではなく、売却して現金化することで、納税に必要な資金を無理なく確保できます。換価分割を前提に遺産分割を進めれば、納税資金の不足に慌てることなく、計画的に相続手続きを進められるでしょう。
④不動産の評価を巡るトラブルを回避できる
不動産を相続する際、評価額を巡ってトラブルに発展するケースがあります。路線価や固定資産税評価額、不動産会社の査定額など、見る指標によって評価にはバラつきがあり、相続人同士で価値の捉え方にズレが生じることは珍しくありません。
例えば同じ不動産でも「2,000万円くらいの価値があるはず」と主張する相続人に対して、「1,200万円が妥当だ」と考える相続人がいれば、話し合いはまとまらないでしょう。
一方で、換価分割なら売却価格を不動産の価値として客観的に評価できます。実際に売却してから不動産の価値を算出できるため、透明性が高くてトラブルを回避しやすくなっています。
第3章 換価分割のデメリット4選
不動産を現金化して公平に分けられるなど、さまざまなメリットがある換価分割ですが、もちろん良い面ばかりではありません。ここでは、換価分割を選択するデメリットを解説します。
①相続税以外に譲渡所得税が課せられる
換価分割では、不動産を売却して得た金銭を法定相続人で分配します。この際、不動産の売却によって生じた利益(譲渡益)には、相続税とは別に譲渡所得税および住民税が課される点に注意が必要です。
譲渡所得にかかる税率は、不動産の所有期間(被相続人の所有期間を引き継ぐ)によって以下のように異なります。
- 所有年数が5年以内(短期譲渡所得):所得税30%+ 復興特別所得税 + 住民税9%
- 所有年数が5年超(長期譲渡所得):所得税15%+ 復興特別所得税 + 住民税5%
②売却手続きに手間と時間がかかる
換価分割を行う際の売却には様々な手続きが伴い、手間と時間がかかります。不動産の売却には、査定の依頼や必要書類の収集、信頼できる不動産会社の選定など、多くの事前準備が必要です。また、不動産会社に査定を依頼してから売却が完了するまでに、半年以上を要するケースが多くなっています。
特に手続きが面倒になりやすいのが、相続人全員の共有名義で不動産を登記した場合です。このようなケースでは、売却時に名義人全員の署名や押印、同意が必要となるため、相続人の人数が多かったり、連絡が取りづらい人がいたりする場合には、手続きが長期化します。
さらに、売却活動の途中で相続人の1人が意思表示を撤回、または価格や売却条件に異議を唱えた場合には、再協議が必要になり、売却手続きがストップしてしまいます。
このように、換価分割は公平な遺産分割方法として有効ですが、売却に至るまでの手続きが煩雑かつ長期化しやすい点は、事前に理解しておく必要があるでしょう。
③すぐに売却できない可能性がある
換価分割では、不動産を売却して得た金銭を相続人間で分配しますが、売却が計画どおりに進むとは限りません。特に地方や築年数の古い物件、相続人が手入れをしていない空き家などは、購入希望者が現れるまでに時間がかかるでしょう。
売却に時間がかかると、相続税の納付期限(相続開始から10ヶ月以内)に間に合わない恐れがあります。換価分割は納税資金の確保にも有効ですが、売却が遅れるとそのメリットを活かせないため注意が必要です。
④不動産仲介手数料などの諸経費が引かれる
不動産を売却する際、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売却価格×3%+6万円+消費税」です。例えば3,000万円で売却した場合、仲介手数料だけで約105万円が差し引かれます。
その他にも、印紙代や登記・抵当権抹消費用といった費用も発生します。これらを差し引いた金額が分配対象となるため、売却金の額面金額よりも受け取れる金額は少なくなることを把握しておくことが大切です。
第4章 換価分割の流れ
換価分割の流れは以下の通りです。
- 換価分割の対象となる財産の価値を調べる
- 遺産分割協議を行う
- 相続財産の名義を変更する
- 相続財産の売却方針を定める
- 売買契約の締結後に売却代金を分配する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP① 換価分割の対象となる財産の価値を調べる
換価分割を行う前に、まずは不動産の評価額を把握する必要があります。相続税の計算に用いる評価額は、土地については路線価方式または倍率方式、建物については固定資産税評価額を基準とするのが一般的です。
ただし、実際の売却価格はこれらの評価額と一致するとは限りません。実勢価格を把握したい場合には、不動産会社に査定を依頼し、具体的な売却見込み額を確認することをおすすめします。複数社に査定を依頼することで、より妥当な相場観を掴めるでしょう。
STEP② 遺産分割協議を行う
換価分割を行うためには、相続人全員が同意する必要があります。1人でも反対する相続人がいれば、換価分割を進めることはできません。合意が得られた場合は、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、全員の署名・押印を行います。
協議書には「不動産を売却し、その代金をどのように分けるか」を明記します。協議書がないまま代金を分配すると、一部の相続人から他の相続人への金銭の移転が贈与と判断され、贈与税の課税対象となるリスクがあります。そのため、換価分割を行う際には、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
STEP③ 相続財産の名義を変更する
不動産の名義が被相続人のままでは、第三者に売却できないため、売却前に法務局に申請し、相続登記(名義変更)を行います。登記名義の決め方には、主に次の2つの方法があります。
- 相続人全員による共有名義にする方法
- 相続人のうち1人の単独名義で登記する方法
換価分割の場合、売却手続きの効率や実務負担を考慮して、代表者1人の名義に変更するケースもあれば、全員で公平性を保つために共有名義とするケースもあります。どちらの方法が適切かは、相続人間の関係性や信頼関係、今後の売却スケジュールなどを踏まえて検討すると良いでしょう。
また、相続登記には以下のような書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 相続放棄申述受理証明書
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書
- 相続登記申請書
申請は自分でも行えますが、不慣れな場合は司法書士に依頼するのがおすすめです。
STEP④ 相続財産の売却方針を定める
名義変更が完了したら、次は不動産の売却に向けて必要な準備と方針決定を行います。具体的には、以下のような項目について定めます。
- 希望売却価格の目安(査定額に対する希望)
- 不動産会社の選定と媒介契約の種類(一般 or 専任 or 専属専任)
- 売却までのスケジュール(納税期限や相続人の都合を考慮)
- 残置物や老朽化の対応(片付け・修繕・解体の必要性)
こうした方針を曖昧なまま進めてしまうと、後になって相続人間で意見が食い違い、売却手続きが中断する恐れがあります。スムーズに換価分割を終えるためにも、売却方針は丁寧に決めておきましょう。
STEP⑤ 売買契約の締結後に売却代金を分配する
不動産の売却が完了したら、事前に取り決めたルールに基づき、売却代金を相続人で分配します。分配の方法や割合は、遺産分割協議書の内容に従って実行されます。
まとめ:換価分割を選択すれば公平な相続を実現しやすい
不動産を含む遺産の分割は、相続人間の意見が分かれやすく、スムーズに進まないケースがあります。そうした場面で、不動産を現金化して平等に分配する換価分割を選択すれば、相続に伴うトラブルを防ぐことが可能です。
また、換価分割には公平性のほか、代償金の負担が不要、納税資金を確保可能といったメリットもあります。相続財産の内容や相続人の状況に応じて換価分割を取り入れることで、現実的な形で相続手続きを終えられるでしょう。
「住まいの賢者」では、相続に強い司法書士と連携し、換価分割に関する相談や登記・分割・売却のサポートを行っています。不動産を含んだ相続でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。