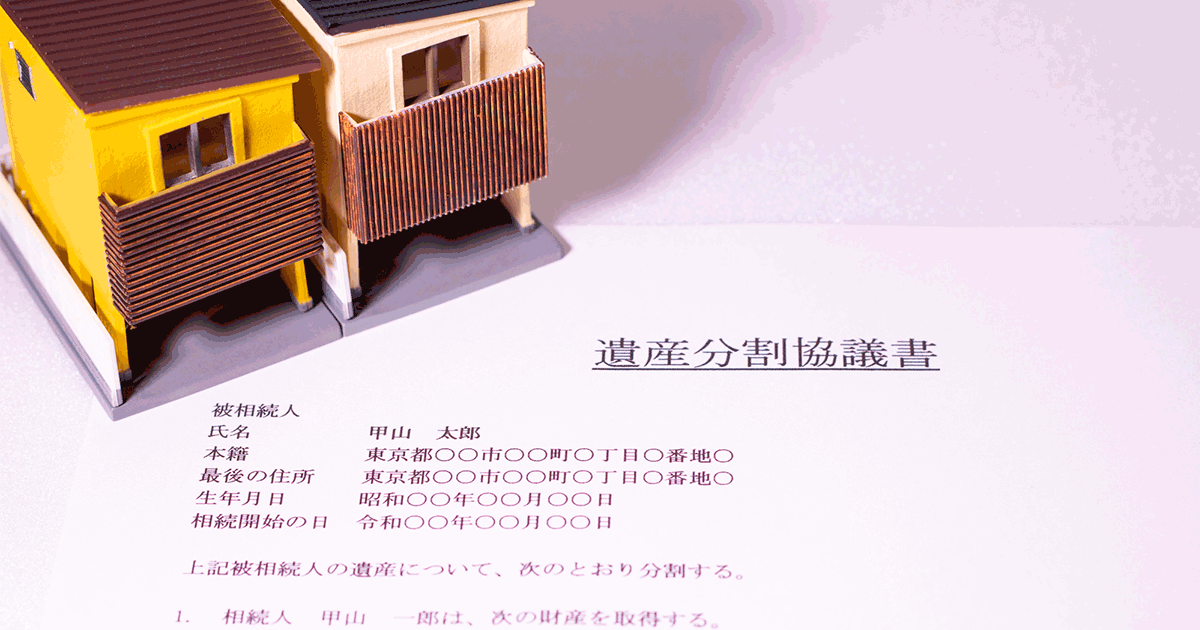目次
はじめに
不動産を相続する際、「共有名義」という形で複数人が所有することは珍しくありません。
特に、親子や兄弟姉妹での相続では、平等な分配を意識して共有名義が選ばれがちです。しかし、その選択が後々のトラブルの火種になることも多く見られます。
本記事では、不動産を共有名義で相続する際に、生じやすいリスクと予防策について解説します。
第1章 不動産の「共有名義」の仕組みとは?
不動産を複数の相続人で引き継ぐ際、代表的な形態の一つが共有名義です。
共有名義になると、各相続人が不動産の一部を所有する形となり、登記簿にそれぞれの持分割合が明記されます。
公平な財産分与を実現する手段として一定の合理性がありますが、運用次第では多大な不都合が生じる可能性も否定できません。
1-1 共有名義や持分の意味
共有名義とは、ひとつの不動産を複数の人が共同で所有することを指します。
この際、各人が保有する権利の割合を「持分」と呼び、登記簿にも「持分2分の1」などと記載されます。持分があれば、不動産の一部について所有権を有することになりますが、利用や処分には制限があります。
例えば、自身の持分を単独で売却することは可能ですが、実際は複数の人に持分があるため売却は現実的ではありません。
また、建物の増改築や貸与、全部の売却などは、自分だけではできないため、他の共有者との合意が必要です。
この合意形成の難しさが、後に大きな問題へと発展する要因となります。持分があるからといって自由に使えるわけではないのが、共有名義の難しいところです。
1-2 共有名義が相続で問題になる理由
共有名義でさらに大変なのは、複数の相続が発生した場合です。時間の経過とともに共有者の一人が亡くなると、持分がさらに相続され、権利関係が複雑化します。
結果として、所有者が多数に分散し、意思決定が著しく困難になります。
例えば、売却や建て替えなどの行為は、共有者全員または持分の過半数の合意が必要になります。合意に至らない場合、相続した不動産は塩漬け状態になりかねません。
このようなリスクは、共有者同士の関係性が希薄になるほど顕在化しやすくなります。
第2章 不動産を共有名義にするメリット・デメリット
共有名義には、表面的な公平性という利点がある一方で、長期的には多くの課題があります。
相続時の選択として共有名義を選ぶ場合は、事前にメリット・デメリットを十分に理解しておきましょう。
では、不動産を共有名義にするメリット・デメリットを解説します。
2-1 共有名義のメリット
共有名義の最大のメリットは、相続人全員が法的に平等な立場で不動産を所有できる点にあります。特に、現金などの他の資産と比べて分割しにくい不動産では、共有とすることで公平感を得やすくなります。
また、管理費や固定資産税といった維持費用を複数人で分担できるため、経済的な負担を軽減する効果も期待できます。
ただし、共有者間の信頼関係と継続的な連絡体制が欠かせません。
2-2 共有名義のデメリット
一方で、共有名義にした不動産の扱いには、共有者全員の合意が必要となる場面が多く存在します。例えば、不動産の売却や建て替えなど行為の種類によって、他の共有者の合意(全員または持分過半数)を求めなければなりません。
共有者の一人が亡くなるたびにその持分がさらに分割され、所有関係はより複雑化します。このような状況に至ると、相続登記が放置されるケースも多く、不動産は事実上「誰も動かせない資産」となってしまう恐れがあるでしょう。
第3章 不動産を共有名義で相続した際のよくあるトラブル
共有名義の不動産を相続した場合、理論上は公平であっても、実際の運用面では多くの問題が発生しやすくなります。
特に、家族間での共有では、話し合いが進まず、結果として不動産の有効活用ができないまま年月が経過する事例も珍しくありません。
では、代表的なトラブル事例を取り上げていきます。
3-1 親子共有だった実家を相続したケース
親子で共有していた実家について、親が亡くなった後、子が単独で所有できると誤解しているケースです。
しかし、親の持分は法定相続人全員に承継されるため、兄弟姉妹間での話し合いが不可欠となります。実家は、財産であると同時に感情的な価値も含んでおり、思い出や愛着が強いほど、法定相続人全員の合意が難しくなる傾向があります。
結果として、居住している兄弟と、遠方に住む兄弟との温度差が顕在化し、対立や不和につながる恐れがあるでしょう。
3-2 兄弟共有の土地で意見が割れたケース
兄弟姉妹間で共有した土地に対し「売却して現金化したい」と考える者と「先祖代々の土地なので残したい」と主張する者との間で意見が一致せず、問題が長期化することがあります。
特に、地方にある土地は市場価値や利用価値の見解が分かれやすく、説得材料が乏しい場合、合意に至るまでに時間を要します。
このような状況下では、土地が放置され、管理費や税金だけが発生する状態が続き、経済的負担の偏りがトラブルの原因となるでしょう。
3-3 放置していたら相続人が増えたケース
相続登記を行わずに長年放置していた結果、次世代の相続が発生し、相続人が大幅に増えるケースもあります。
相続人が増えた状態では、所有者の特定が困難になるだけではなく、結果的に不動産が塩漬け状態に陥るケースも珍しくありません。
第4章 共有名義のまま相続が発生したケース
共有者が亡くなった際、持分が相続の対象となることで、権利の複雑化が発生します。
所有者が一人から複数、さらに世代をまたいで増加していくことで、法的にも事務的にも処理が難しくなる恐れがあるでしょう。
特に、登記を怠ったまま相続が重なった場合には、所有者の特定が困難となり、法的な手続きにおいても大きな障害となります。
4-1 被相続人の持分は相続人に承継される
共有名義の不動産において、共有者の一人が亡くなった場合、持分は相続人にそのまま承継されます。
例えば、兄弟で2分の1ずつの共有状態にあった不動産で片方が死亡した場合、その持分は故人の配偶者や子に分配され、新たな共有者が加わる形になります。
よって、意思決定の難易度が上がり、売却や活用の話が進まなくなるリスクが高まります。トラブルを避けるためには、早期の登記と権利関係の整理が必要です。
第5章 共有名義の不動産を相続したあとの対処法
共有名義で相続した不動産は、適切に管理・活用しなければ、次第に経済的負担が増大していきます。
家族間の合意が曖昧なまま放置されると、物件の価値が低下するばかりか、親族関係の悪化や税負担の増加などの問題も招きかねません。
では、共有名義の不動産を相続したあとの対処法を解説します。
5-1 管理・費用分担のルールを明確にする
不動産の維持管理には、固定資産税や修繕費などのコストが継続的に発生します。
固定資産税や修繕費などの費用について、共有者間であらかじめ負担割合を決めておかないと「誰がどこまで負担すべきか」などの不公平感からトラブルに発展する可能性があります。
また、費用分担だけではなく、管理責任者の指定や連絡体制、支払いの流れなども含めて、文書による取り決めを行うのが望ましい対応です。
合意内容を契約書として明文化することで、トラブル防止につながります。
5-2 売却や共有解消を検討する
共有名義のままで管理が難しいと感じた場合は、早い段階で売却や共有状態の解消を検討する必要があります。
不動産を売却すれば、現金を持分に応じて分けられるため、公平性を確保しやすくなります。また、共有者の一人が他の持分を買い取る「持分買取」を行うという手段もあります。
ただし、いずれも法的・税務的な観点からの検討が必要であり、単独での判断はリスクを伴います。信頼できる専門家に相談しながら進めながら進めましょう。
第6章 共有名義の相続で困らないための予防策
相続トラブルの多くは、生前の備え不足や相続発生後の対応の遅れによって引き起こされます。
共有名義による相続はその典型例であり「平等な分け方」がかえってトラブルとなりやすいのが現実です。リスクを回避するためには、相続発生前からの備えと発生後の迅速な対応が大切です。
では、共有名義の相続で困らないための予防策を解説します。
6-1 生前に対策をする
不動産の相続において、最も確実なトラブル回避策は、被相続人が生前に明確な意思を示しておくことです。
例えば、特定の相続人に生前贈与を行うことで、不動産を単独所有とすることが可能になります。また、遺言書の作成によって、誰がどのように相続するのかをあらかじめ指定しておけば、遺産分割協議による対立を避けることができます。
いずれの場合も、税金面を踏まえて慎重に手続きを進める必要があるため、専門家に相談しながら検討するとよいでしょう。
6-2 相続発生後にすぐ動く
相続が発生してからは、時間との勝負です。
遺産分割協議や登記手続きなどを迅速に進めなければ、関係者の数が増えたり、話し合いが困難になったりする恐れがあります。
特に、共有名義にするか単独名義にするかの判断を先送りにすると、後になってからの合意が難航しやすくなります。
不動産の活用計画や税務対応などの課題も含めて、相続発生直後に専門家に相談しながら全体の方針を決めておくことが大切です。
6-3 専門家に相談する
不動産相続は、ただ財産を分配するだけではなく、納税や登記など多分野の知識が必要です。特に、共有名義の問題は複雑で、個人間での対処には限界があります。
司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けられます。
相続人とのトラブルを防ぐためにも、早めに第三者のサポートを受けることがおすすめです。初動を誤らないためにも、できるだけ相続発生前からの準備が望ましいでしょう。
まとめ:共有名義の不動産はトラブルが多い!早めに専門家に相談しよう
不動産を共有名義で相続すると「平等な財産分与」という表向きのメリットがあります。
しかし、実際には管理や意思決定が煩雑になりやすく、相続人どうしの関係を悪化させる火種になりかねません。
トラブルを回避するためには、相続前の対策と、相続発生後の迅速な対応が欠かせません。
共有名義を前提とするのではなく、単独名義や売却などの選択肢も視野に入れ、納得のいく選択肢を選びましょう。
「住まいの賢者」では、相続を得意とする司法書士と連携し、相続不動産の調査から登記、売却、活用までをワンストップで支援するサービスを提供しています。
初回相談・査定は無料で行っており、売却先のマッチングや税理士との連携も可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。