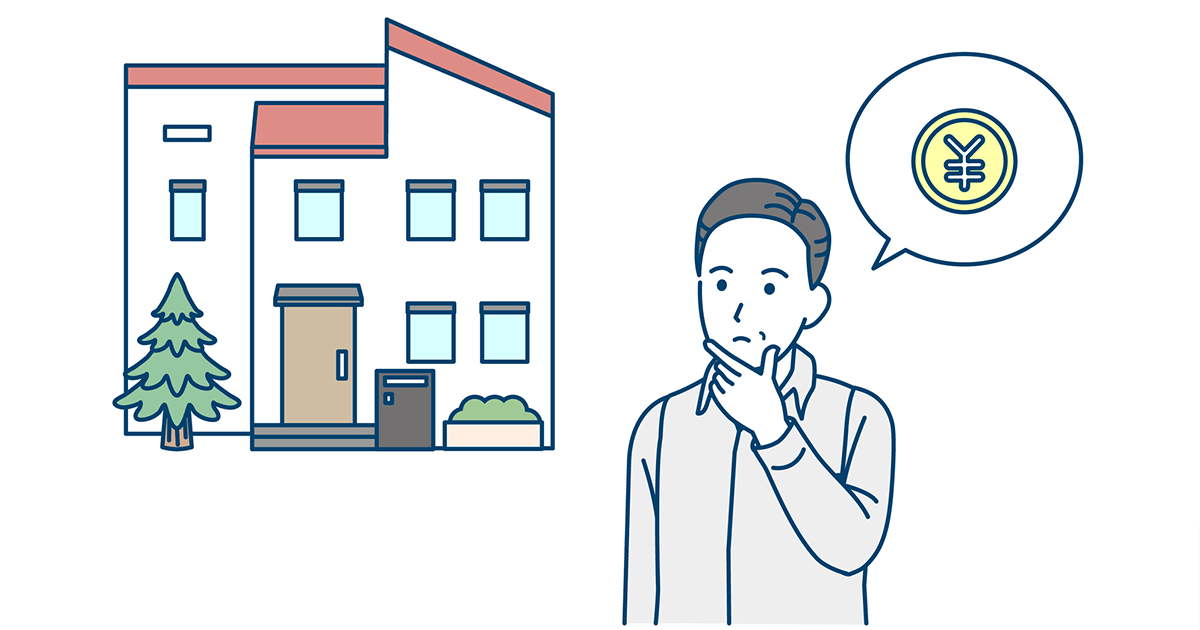目次
はじめに
通常、不動産を取得した際は不動産取得税がかかります。しかし、故人の不動産を相続した際は、原則、不動産取得税がかかりません。ただし、相続税や登録免許税は発生するため、この点に戸惑う方は多くいます。また、相続の方法や形式によっては相続した際に不動産取得税がかかるケースがあり、この点も戸惑いがちな点です。
この記事では、なぜ故人の不動産を相続した際に原則不動産取得税がかからないかを解説していきます。そのうえで、例外的に不動産取得税がかかるケース、不動産取得税の計算方法や相続時にかかる税金についてわかりやすく解説します。
第1章 相続では不動産取得税はかからない
1-1 相続では不動産取得税がかからない理由
故人の不動産を相続した際に不動産取得税がかからない理由は、「取引による不動産の取得ではない」と考えられているためです。
不動産取得税は、一般に不動産の売買や贈与、建築があった際に発生する税金です。これは、課税対象者が自分の意思で不動産を取得することを前提としています。
これに対し、相続による不動産の取得は、特定のケースを除き、相続人の意思によらず発生する事由と考えられます。そのため、故人の不動産を相続により取得した際は、取引以外の形で不動産の取得があったと考えられ、不動産取得税はかかりません。
第2章 故人の不動産を受け継いで不動産取得税がかかる3つのケース
第1章でお伝えした通り、原則相続では不動産取得税はかかりません。しかし、以下の3つのケースでは、相続による不動産の取得でも不動産取得税がかかります。
2-1 法定相続人以外が特定遺贈によって取得した
法定相続人とは、民法で定められた「亡くなった人が持つ財産を受け継ぐ権利を有する人」のことです。具体的には、被相続人の配偶者と血族(子や孫、実父母や実祖父母)がこれに当たり、内縁関係の家族は法定相続人としては認められません。
法定相続人以外が特定遺贈によって故人の不動産を取得した際は、不動産取得税がかかります。
特定遺贈は、故人があらかじめ用意していた遺言書の中で「遺産のうち具体的な資産を指定して残す方法」です。例えば、「法定相続人であるAさんには現金1,000万円を、法定相続人でないBさんには所有している不動産を残す」と遺言書の中で明言することがこれに当たります。
この際、法定相続人以外が不動産を引き継ぐ行為は、不動産を贈与されたのと同一の扱いとなり、不動産取得税がかかることとなります。
2-2 死因贈与によって取得した
死因贈与によって不動産を取得した際は、不動産取得税がかかります。これについては、法定相続人かどうかを問いません。
死因贈与とは、生前に死亡を前提とする贈与契約を結ぶことです。例えば、Aさんが孫であるBさんに「自分が死んだら不動産をあげる」と伝えており、Bさんが「ありがたくもらいます」と同意をしている状態がこれに当たります。これは、生前に贈与をしている状態と同一と見なされるため、不動産取得税が発生します。
2-3 相続時精算課税制度によって取得した
相続時精算課税制度によって不動産を取得した際も、不動産取得税がかかります。
相続時精算課税制度とは、原則「60歳以上の父母、もしくは祖父母」から「18歳以上の子、もしくは孫」に対して、贈与をした際に選択できる贈与税の制度です。この制度を使用した場合、贈与税を計算する際に2,500万円の特別控除が適用されます。
この制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、最終的な相続税が計算されます。不動産の所有権移転の形式としては、通常の贈与と同様に扱われるため、不動産取得税が発生します。これは、死因贈与の場合と同様の考え方です。
第3章 不動産取得税を計算する方法
相続した不動産に不動産取得税がかかる場合の計算方法について解説します。不動産取得税の計算方法は以下の通りに定められてます。
- 相続した土地・家屋の固定資産評価額×3%
- 非住宅家屋の場合、固定資産評価額×4%
- 居住用の土地・家屋を取得した場合、軽減措置がある
例えば、土地・家屋合わせて4,000万円の固定資産評価額の不動産を取得した場合、4,000万円×3%で120万円の不動産取得税が発生します。また、店舗や倉庫、工場などの固定資産評価額1億円(建物8,000万円、土地2,000万円)の非住宅家屋を取得した場合、8,000万×4%+2,000万×3%で合計380万円の不動産取得税が発生します。なお、固定資産評価額は不動産の購入価格のことではなく、毎年更新される固定資産評価証明書によって確認することとなっています。
また、2025年6月現在、居住用の土地・家屋を取得した場合は税額の軽減措置があります。軽減措置の内訳や計算方法は、取得した不動産が新築住宅か中古住宅かによって変わります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たす建物が軽減措置の対象です。
- 個人の居住を目的とすること
- 床面積が50㎡以上(一戸建て以外の貸家の場合は40㎡以上)240㎡以下であること
これらの新築住宅については、固定資産税評価額から1,200万円が軽減されます。認定長期優良住宅の場合は軽減額が1,300万円になるため、相続した不動産の性質は注視しておいてください。
なお、軽減措置は2026年3月31日まで適用可能となっています。それ以降の相続では、その時点での法律に基づく措置となるので、最新の情報に注視してください。
また、新築住宅を構える土地について以下の条件を満たす場合に軽減措置が取られます。
- 建物が軽減措置の対象であること
- 土地を取得してから3年以内に建物を新築すること
- 建物の建築が先だった場合、1年以内にその土地を取得していること
これらの条件を満たした土地を令和4年4月1日以降に取得した場合、45,000円または「土地1㎡あたりの固定資産税評価額の1/2×課税床面積(200㎡まで)×2×3%」のいずれか高い方が軽減されます。
具体例として認定長期優良住宅に認定された固定資産評価額3,000万円の建物・土地1㎡あたりの固定資産評価額5万円の土地150㎡の新築住宅を用いて計算します。この場合、不動産取得税は以下の通りです。
- 建物:(3,000万-1,300万)×3%=510,000円
- 土地:5万×1/2×150*2*3%=225,000円 これが課税標準額と同額のためゼロ円
よって、上記不動産の場合は510,000円の不動産取得税が発生します。
中古物件の場合、以下の条件を満たす建物が軽減措置の対象です。
- 個人の居住を目的とした住宅であること(別荘等も可)
- 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
- 昭和57年1月1日以降に新築されたものであること、または、昭和30年7月1日以降昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることが証明されているものであること
- 前項に当てはまらない場合、以下の要件をすべて満たしていること
・床面積が50㎡以上240㎡であること
・取得した人が、耐震改修工事を行うこと
・耐震改修工事後の住宅が、建築士等による耐震診断等により耐震基準に適合していることが証明されていること
・昭和30年7月1日以降の建築物であること
・取得日から6ヶ月以内に居住すること
上記を満たした場合に限り、軽減措置を受けられます。なお、土地の軽減措置の要件や計算方法は新築住宅と共通です。中古住宅で受けられる軽減措置の控除額は、建物が建築年月日によって変わることとなっており、新しく建築された物件ほど控除額が大きくなります。
具体例として、昭和43年3月1日に建築された、固定資産評価額500万円の建物・土地1㎡あたりの固定資産評価額5万円の土地150㎡の新築住宅を用いて計算します。この場合、不動産取得税は以下の通りです。
- 建物:(500万-230万)×3%=81,000円
- 土地:5万×1/2×150*2*3%=225,000円 これが課税標準額と同額のためゼロ円
よって、上記不動産の場合は81,000円の不動産取得税が発生します。
第4章 不動産を相続したときにかかる税金
4-1 相続税
相続税は、不動産以外も含めたすべての遺産総額から計算される税金です。相続税額は以下の形で計算します。
- 課税価格{遺産総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定代理人の人数)}×税率-控除額
相続税の税率は、遺産総額から基礎控除額を引いた課税価格によって変動し、少なくとも10%、最大で55%の税率がかかります。なお、控除額も課税価格が増えるほど増額されます。
具体例として、以下のケースでの相続税を計算します。
- 遺産総額:不動産4,000万円のみ
- 法定相続人:1人
この場合、課税価格は「4,000万-(3,000万+600万×1人)=400万円」です。この場合、税率は10%・控除額はなしとなるため、最終的な相続税は「400万円×10%=40万円」です。
なお、不動産評価額は固定資産評価証明書によって確認することができます。ただし、何らかの事情で固定資産評価証明書を取得できない場合、税理士や不動産鑑定士などの専門家に不動産の評価額を算出してもらう必要があります。
4-2 登録免許税
登録免許税は、相続した不動産の登記手続きをする際、国に支払う税金です。登録免許税の計算式は、所有権移転の方法によって変わります。
単純な相続によって不動産を取得した際の登録免許税は、「不動産評価額×0.4%」と定められています。例えば、不動産評価額2,000万円の建物・土地の登録免許税は8万円です。
一方、贈与によって不動産を取得した際の登録免許税は、「不動産評価額×2%」となっています。不動産評価額2,000万円の建物・土地を贈与によって取得した場合の登録免許税は40万円です。
まとめ:不動産の相続手続きについてお気軽にお問い合わせください
この記事では、相続した不動産に不動産取得税が原則かからない理由・不動産取得税が発生する条件と、不動産を相続した際に発生する税金について解説しました。
不動産の相続手続きはかなり煩雑なほか、どの程度の税金が発生するかを計算するための必要資料を収集するのも複雑です。また、相続をするにあたってどの手段で財産を遺すのが最も税負担が軽いかの見極めも難しい部分です。
「住まいの賢者」では、不動産の相続に強い司法書士と連携し、相続手続きに関する相談や依頼を受け付けています。不動産の相続手続きでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合せください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。