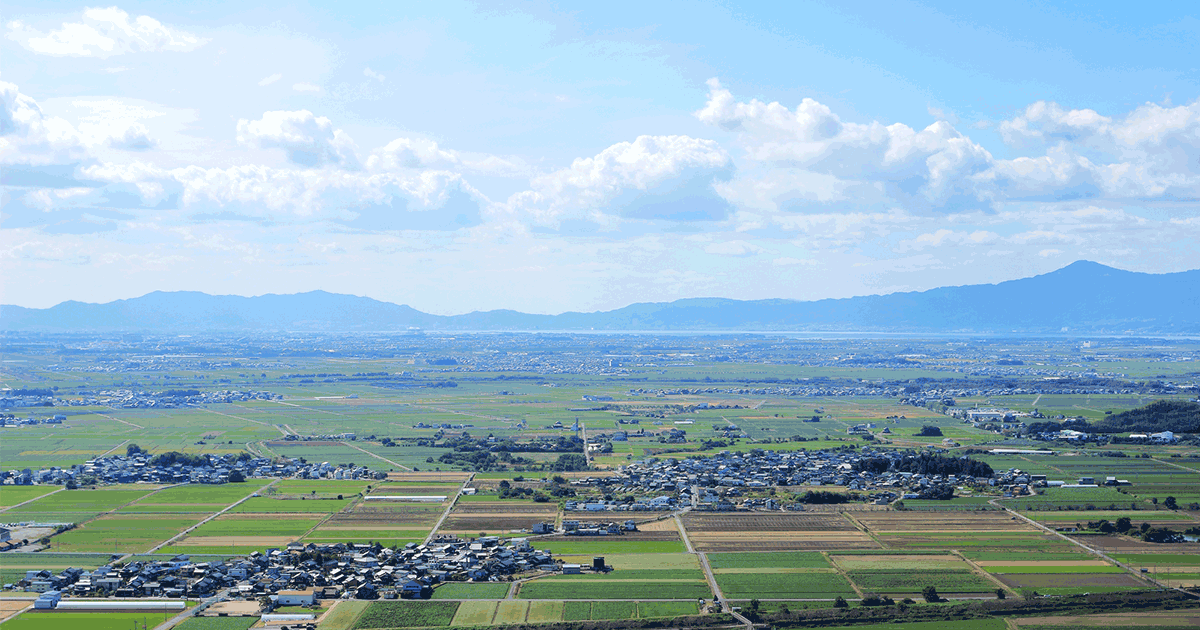目次
はじめに
相続したものの使い道がない、維持管理も難しい――そんな土地を「手放したい」と感じる方が近年増えています。その対策として登場したのが、2023年4月施行の相続土地国庫帰属制度です。
この制度を利用すれば、一定の条件を満たした相続土地を国に引き取ってもらうことができます。しかし、制度を利用するには審査手数料や負担金が必要で、予想以上の金額に戸惑う方も少なくありません。
本記事では、相続土地国庫帰属制度における手数料や負担金の目安、そして「高い」と感じたときの代替手段について、実務的な視点から詳しく解説します。
第1章 相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続により取得した不要な土地を、一定の条件のもとで国が引き取ってくれる制度です。所有者不明土地の増加防止を目的とし、2023年4月27日に施行されました。
申請は法務局を通じて行い、審査に通るとその土地の所有権は国へ移転します。これにより、固定資産税の納税義務や土地管理の責任から解放されます。
ただし、制度を利用するためには以下のような要件を満たしている必要があります。
- 土地に建物が存在しないこと
- 境界が明確であること
- 担保権や通行権などが設定されていないこと
そのため、誰でも自由に手放せるわけではなく、「条件付きの引き渡し制度」であることを理解しておく必要があります。
第2章 相続土地国庫帰属制度の審査手数料はいくら?
制度を利用するには、まず審査手数料を納める必要があります。この金額は土地1筆につき14,000円と定められており、申請時に収入印紙で納付します。
なお、「筆」とは登記上の土地の単位を指し、たとえ隣接していても別々の登記になっていれば複数の筆とみなされ、それぞれに手数料がかかります。
また、申請を取り下げた場合や審査で不承認となった場合でも、手数料は返還されないため注意が必要です。
第3章 相続土地国庫帰属制度の負担金はいくら?
審査に通ったあとは、負担金を納める必要があります。金額は土地の用途(地目)や面積により異なり、以下が目安です。
宅地
原則として一筆あたり20万円です。ただし、市街化区域内や用途地域に属する宅地については、面積に応じて負担金が加算される仕組みです。
例:100㎡で約55万円、200㎡で約80万円になるケースもあります。
田畑
田んぼや畑についても原則20万円が基本ですが、農業振興地域内などの指定地では面積によって増額されることがあります。
例:100㎡で約55万円、200㎡で約80万円程度となることもあります。
森林
森林は一律金額ではなく、面積や免責条件に応じて個別に計算されます。
例:1,500㎡で約27万円、3,000㎡で約30万円など。
その他の地目(雑種地・原野など)
原則は20万円ですが、市街地にある場合などは宅地と同様に面積での加算が発生することがあります。
例:都市計画区域内で100㎡の場合、約55万円となることもあります。
第4章 相続土地国庫帰属制度で発生するその他の費用
相続土地国庫帰属制度を利用する際には、審査手数料や負担金だけでなく、申請準備や土地の状態に応じてさまざまな追加費用が発生することがあります。予算を見積もる際には、これらのコストも踏まえておくことが重要です。
以下に、主な追加費用とその概要をご紹介します。
4-1 書類取得費用
申請には、登記事項証明書、公図、地積測量図などの法務局発行書類が必要です。これらは1通あたり数百円〜1,000円程度ですが、筆数が多い場合や複数書類が必要な場合には、意外とまとまった金額になります。
4-2 専門家への依頼費用
制度の申請手続きは煩雑で、書類の作成や土地の調査に一定の専門知識が求められます。そのため、以下のような専門家へ依頼するケースが一般的です。
- 司法書士・行政書士・弁護士の報酬:10万〜50万円程度
- 土地家屋調査士(測量や仮杭設置等):15万〜30万円程度
専門家に依頼することでミスや手戻りを防げる反面、予想以上に費用がかさむこともあるので、必ず見積もりを取っておきましょう。
4-3 境界確定費用
土地の境界が不明確な場合は、確定測量を行い、隣地所有者との立会いや協議を行う必要があります。この費用は、一般的に30万円〜80万円程度とされ、地形や隣接関係によって変動します。
特に古い土地や測量図のない土地では、追加の費用と時間がかかるため注意が必要です。
4-4 建物や工作物の撤去費用
制度の対象となるのは「更地」であるため、古い建物、倉庫、井戸、物置、コンクリート塀などが残っている場合は撤去が必須です。
撤去費用は対象物や解体規模によって異なりますが、10万〜100万円超となることもあります。
4-5 その他の諸費用
- 印紙代、郵送費、交通費などの細かな実費
- 市町村や関係機関への申請補助書類の取得費
- 必要に応じた再測量や補正資料の費用 など
第5章 相続土地国庫帰属制度の負担金が高いと感じたときの対処法
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放す手段として注目されていますが、申請には負担金や諸費用が発生します。
特に都市部や農業振興地域の土地では、面積に応じて数十万円単位の負担金がかかるケースもあり、「思ったより高い」と感じる方も少なくありません。
そうした場合は、この制度を使わずとも検討できる他の選択肢があります。ここでは、代表的な4つの対処法を紹介します。
5-1 相続放棄を検討する
相続する土地の負担が大きすぎると感じた場合、そもそも相続自体を放棄するという方法があります。家庭裁判所に相続放棄を申し立てれば、当該土地を含むすべての相続財産の権利・義務を放棄できます。
ただし、相続放棄には以下の注意点があります。
- 自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に手続を行う必要があること
- 土地以外の預貯金や有価証券など、他の財産もまとめて放棄することになること
- 現にその土地を使用・管理している場合、管理義務が一時的に残ること
相続財産全体の内容や家庭の状況を踏まえ、慎重に判断する必要があります。
5-2 土地を活用して収益化する
手放す代わりに、相続した土地を積極的に活用するという選択肢もあります。たとえば以下のような活用法があります。
- 宅地であれば、月極駐車場や賃貸住宅を建てる
- 農地であれば、自ら農業を始める/農地バンクに貸し出す
- 原野なども、資材置き場やソーラーパネル用地として転用できることがある
初期費用や管理の手間はかかりますが、土地が収益源となることで、国庫帰属制度で浮かせられる費用を上回る経済的メリットが得られる可能性もあります。
5-3 土地を売却して処分する
相続した土地を売却することができれば、費用負担を回避できるだけでなく、資金を手に入れることもできます。
売却方法としては以下のような手段があります。
- 不動産仲介会社を通じて一般売却する
- 隣接地所有者に打診して買い取ってもらう
- 空き家バンクや地域の物件マッチング制度を活用する
市街地であれば比較的売却しやすい一方、山間部や田畑・原野などは買い手がつきにくいこともあります。
いずれにしても、できるだけ早期に行動を起こすことがポイントです。
5-4 土地を贈与・寄付する
土地を第三者に贈与したり、自治体やNPO法人などへ寄付するという方法もあります。公共団体や地域活動団体が土地を必要としている場合には、受け入れられる可能性があります。
ただし、以下のような注意点があります。
- 受け入れ先が土地を管理・活用できる体制にあるか確認すること
- 個人や法人への贈与では、譲渡所得税や贈与税が発生する場合があること
- 所有権移転登記などの手続が必要になること
寄付・贈与はあくまで「相手の合意」が前提ですので、事前の相談と条件確認が不可欠です。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、管理に困る不要な土地を国に引き取ってもらえる画期的な制度ですが、審査手数料や負担金などの費用が発生します。事前にコストを把握し、他の選択肢と比較しながら冷静に判断することが大切です。
特に負担金が高額に感じられる場合には、相続放棄、活用、売却、寄付といった別の方法を検討し、自分と土地の将来にとって最善の選択をしていきましょう。「住まいの賢者」では、相続や不動産に関するご相談を、司法書士や税理士と連携してワンストップでサポートしています。
まずは無料相談にて、現状やお悩みをお聞かせください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。