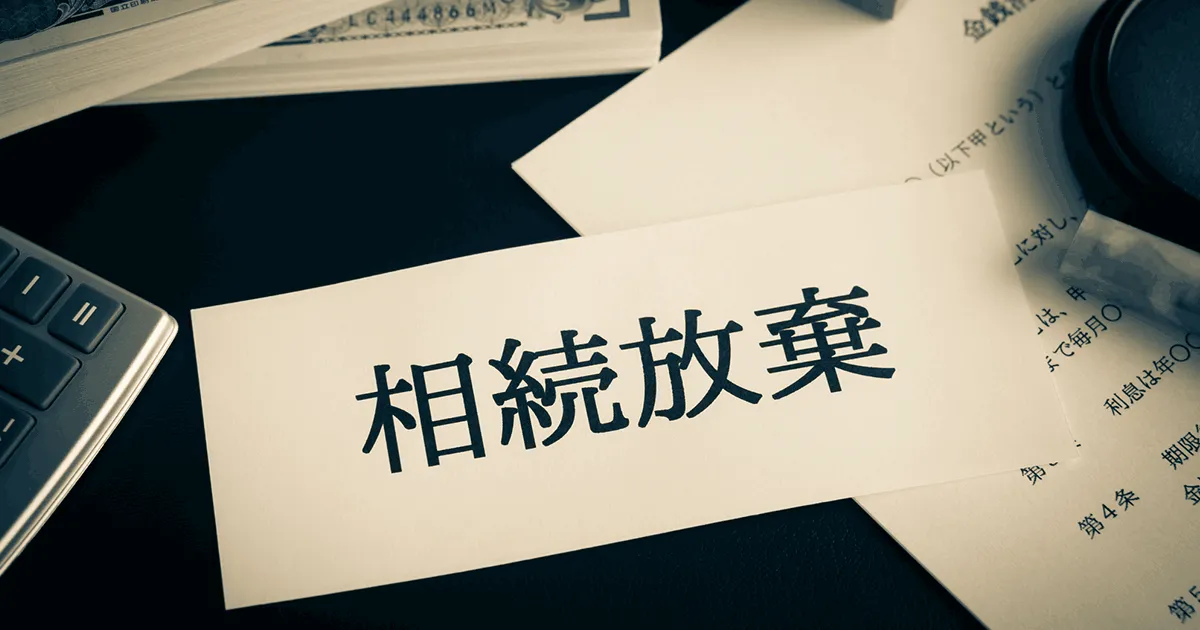目次
はじめに
相続した土地が管理困難だったり、利用予定がなかったりする場合、手放したいと考える方も多いでしょう。しかし、相続放棄には期限や条件があり、すべてのケースで認められるわけではありません。
特に、「熟慮期間」を過ぎてしまったり、遺産を使用・処分してしまった場合には、相続放棄が不可能となります。また、相続放棄は相続財産全体に対して行うものであり、特定の財産だけを放棄することはできません。
この記事では土地を相続放棄できないケースや、相続放棄以外で土地を手放す方法について解説します。
第1章 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を一切受け継がないことを選択する手続です。相続放棄により、相続人は初めから相続人でなかったとみなされます。
また、相続を放棄せず要らない土地を持ち続けた場合には、「固定資産税が課せられる」「管理義務が必要になる」「何かあったときの所有者責任を負わなければならない」などのデメリットが生じます。
相続放棄を検討する際は、相続財産の内容や債務の有無を確認し、慎重に判断することが重要です。また、不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
第2章 土地を相続放棄できないケース
2-1 相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまった
相続放棄を行うためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼び、期間を過ぎると相続放棄が認められなくなります。
熟慮期間を過ぎてしまった場合、相続人は被相続人の財産や債務をすべて受け継ぐ「単純承認」を行ったものとみなされます。
2-2 遺産を使用・処分してしまった
相続放棄を希望していても、遺産をすでに使用または処分している場合、相続放棄が認められず、「法定単純承認」となります。
具体的には、相続財産を売却したり、預金を引き出して使用したりする行為です。また、被相続人の債務を返済するために遺産を使用した場合も、単純承認とみなされる可能性があります。
ただし、相続財産の保存行為や、相続財産の調査・管理のための行為は、単純承認には該当しません。たとえば、相続財産の目録作成や、必要最低限の管理行為は問題ないとされています。
2-3 相続放棄の必要書類が不足していた
相続放棄を行う際には、家庭裁判所に必要な書類を提出する必要があります。これらの書類が不足していたり、不備があったりすると、相続放棄の申述が受理されません。
主な必要書類には、相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などがあります。また、申述人1人につき800円の収入印紙や郵便切手代などの費用も必要です。
書類の不備がある場合、家庭裁判所から補正の指示があることもありますが、補正が間に合わないと、申述が却下される可能性があります。そのため、書類の準備は慎重に行う必要があります。
第3章 【注意】土地だけを相続放棄することはできない
相続放棄は、被相続人の財産全体を対象とする手続であり、特定の財産だけを選んで放棄することはできません。つまり、土地だけを相続放棄し、他の財産を相続することは法律上認められていないのです。
このような選択的な相続放棄は、民法の規定に反します。不要な土地だけを手放したい場合でも、相続放棄を選択すると、預貯金やその他の資産も含めてすべての相続権を失うことになります。
第4章 土地を相続放棄せずに手放す3つの方法
方法① 売却する
相続した土地を手放すための最も一般的な方法は、売却です。売却には主に「仲介」と「買取」の2つの手段があります。
「仲介」は、不動産会社を通じて一般の買主を探す方法で、市場価格またはそれに近い価格での売却が期待できます。ただし、買主が見つかるまで時間がかかるケースが多く、物件の状態によってはリフォームが必要となる場合もあります。
一方、「買取」は、不動産会社が直接土地を買い取る方法で、短期間での現金化が可能です。価格は市場価格よりも低くなる傾向がありますが、契約不適合責任(隠れた欠陥があった場合、売主が買主に対して負う責任)を免責できるメリットがあります。
方法② 相続土地国庫帰属制度を活用する
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈により取得した土地を、一定の条件を満たすことで国に引き取ってもらえる制度です。この制度は、2023年4月27日から施行され、管理が困難な土地を手放す新たな選択肢として注目されています。
制度を利用するには、土地が一定の要件を満たしている必要があります。要件とは、建物が存在しないことや、土壌汚染がないことなどです。申請者は、法務局に対して申請を行い、審査を経て承認されると、所有権が国に移転します。
申請には、1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。また、審査に通過した場合は、土地の種類や面積に応じた負担金を納付する必要があります。例えば、宅地であれば200㎡で約79万円、農地であれば同面積で約45万円です。
方法③ 贈与・寄付する
相続した土地を手放す方法として、第三者への贈与や公共団体・団体への寄付も選択肢の一つです。これらの方法を実行する際には、相続登記を行い、自身が正式な所有者であることを明確にする必要があります。
贈与の場合、贈与契約書の作成や登記手続が必要となります。また、受贈者には贈与税が課される可能性があるため、税務上の影響を事前に確認することが重要です。
寄付を検討する場合、寄付先の団体や自治体が土地を受け入れるかどうかを確認する必要があります。特に、土地の状態や立地条件によっては、受け入れを拒否される場合もあるでしょう。
第5章 土地を相続放棄するときの注意点
土地を相続放棄する際に手続を誤ると、意図せず相続を承認したとみなされる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
土地を相続放棄するときの主な注意点は、次の3項目です。
- 熟慮期間に間に合わない場合には伸長申立てを行う
- 相続人全員が放棄すると次の順位の相続人に相続権が移る
- 相続放棄後も土地の管理義務が残る場合がある
5-1 熟慮期間に間に合わない場合には伸長申立てを行う
相続放棄の熟慮期間内に相続放棄の申述が間に合わない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です。ただし、あくまで熟慮期間内に行う必要があり、期間を過ぎてからの申立ては認められません。
また、熟慮期間の延長が認められるのは、相続財産の調査に時間がかかったり、相続人の所在がわからないなど、正当な理由がある場合です。「仕事が忙しいから」といった理由では、簡単には認められません。
5-2 相続人全員が放棄すると次の順位の相続人に相続権が移る
相続人全員が相続放棄を行った場合、相続権は次順位の相続人へ移ります。民法では、相続順位が定められており、第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。
相続放棄をした相続人には、次順位の相続人に通知する法的義務はありません。また、家庭裁判所も次順位の相続人に通知を行わないため、次順位の相続人が相続権を持つことを知らないまま、債権者からの督促で初めて気づくケースもあります。
相続放棄をした相続人には、次順位の相続人に通知する法的義務はありません。また、家庭裁判所も次順位の相続人に通知を行わないため、次順位の相続人が相続権を持つことを知らないまま、債権者からの督促で初めて気づくケースもあります。
5-3 相続放棄後も土地の管理義務が残る場合がある
2023年4月の民法改正より前では、相続放棄をした者が相続財産の管理を続けなければならない場合がありましたが、改正後は「現に占有している」者に限り、相続放棄後も管理義務(保存義務)を負うこととなっています。
「現に占有している」とは、被相続人の財産を事実上支配・管理している状態です。例えば、被相続人と同居していた相続人がそのまま居住を続けている場合です。一方、相続財産を占有していない相続人は、管理義務を負わないこととなりました。
とはいえ、実際に相続財産を占有していると相続放棄後も適切な管理が必要です。管理を怠った結果、第三者に損害が生じた場合、損害賠償責任を問われます。管理義務を免れたい場合、相続財産清算人の選任を申し立てるのも一つの方法です。
まとめ
土地の相続放棄には、熟慮期間の経過や遺産の使用・処分、必要書類の不備など、放棄が認められないケースがあります。また、相続放棄は財産全体に対して行うものであり、特定の財産だけを放棄することはできません。
相続放棄ができない場合でも売却、相続土地国庫帰属制度の利用、贈与・寄付などの方法はありますが、いずれも相続登記が必要です。土地を相続放棄する際は、熟慮期間や次順位の相続人への影響、放棄後の管理義務などに注意しましょう。
「住まいの賢者」では、相続登記・協議書作成・売却手続き・税務申告のご相談まで、司法書士や税理士と連携した一括支援をご提供しています。まずは無料相談で、現状とご希望をお聞かせください。
不動産の無料相談なら
あんしんリーガルへ
電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。
「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。